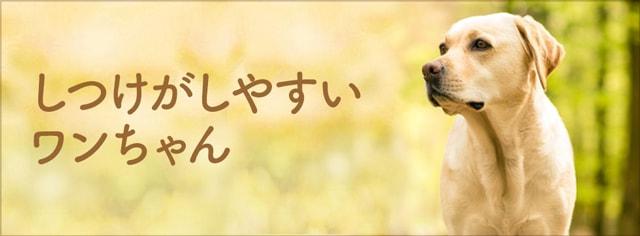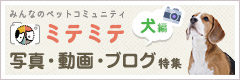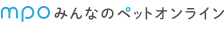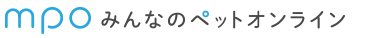犬の多頭飼いに必要な心構え

多頭飼いを始めるためには、まず下記の条件をクリアする必要があります。
犬を2匹以上飼うスペースを確保できるか
室内や室外で犬を飼うためには、体の大きさや運動量に合わせたスペースの確保が必要です。
犬が安心できる場所としてケージやサークルを用意しますが、2匹以上になると当然必要なスペースは1匹のときより広くなります。
犬が安心できる場所としてケージやサークルを用意しますが、2匹以上になると当然必要なスペースは1匹のときより広くなります。
犬を2匹以上飼う経済的余裕はあるか
毎日のフードやおやつ、ペットシーツなどの消耗品代、病院代、ワクチン、フィラリア、トリミング費用。犬が2匹以上に増えるということは、飼育にかかる費用も2倍、3倍に増えるということです。
特に急病で病院にかかるときなど、思いがけず高額な費用を請求される場合もあります。
特に急病で病院にかかるときなど、思いがけず高額な費用を請求される場合もあります。
犬の世話に必要な時間を確保できるか
月齢や犬種に合ったフードの準備や毎日の散歩、トイレ、ブラッシングやシャンプーのお手入れなど、多頭飼いの場合でも、1匹1匹対応することが求められます。
また、パートナーとしての信頼関係を築くためには、犬とスキンシップをとる時間も欠かせません。
つまり犬が増えるだけ、その世話にかかる時間も増えるということです。
また、パートナーとしての信頼関係を築くためには、犬とスキンシップをとる時間も欠かせません。
つまり犬が増えるだけ、その世話にかかる時間も増えるということです。
犬の多頭飼いのメリット・デメリット

次に、犬を多頭飼いするメリットやデメリットはどんなことでしょうか。
飼い主として、多頭飼いのいい面だけではなく、悪い面もしっかり理解しておくことが求められます。
飼い主として、多頭飼いのいい面だけではなく、悪い面もしっかり理解しておくことが求められます。
メリット
・犬同士で生活することで社会性が身につく
もともと犬は群れで生活していた動物です。子犬の頃からほかの犬と接し、共に成長することで、社会性を身につけることができます。
・留守番の負担が減らせる
特に飼い主が仕事で長時間家を空けるときなど、多くの犬にとって1匹での留守番は大きなストレスです。
相性がよい犬同士の多頭飼いであれば、飼い主がいない寂しさを紛らわすことができるため、ストレスの軽減にもつながります。
・犬による性格や特徴の違いを楽しめる
たとえ同じ犬種だとしても、性格や成長具合はさまざま。異なる犬種であれば、さらに差がハッキリと見えてきます。
犬それぞれの違いを楽しめるのも、多頭飼いならではのメリットと言えるでしょう。
もともと犬は群れで生活していた動物です。子犬の頃からほかの犬と接し、共に成長することで、社会性を身につけることができます。
・留守番の負担が減らせる
特に飼い主が仕事で長時間家を空けるときなど、多くの犬にとって1匹での留守番は大きなストレスです。
相性がよい犬同士の多頭飼いであれば、飼い主がいない寂しさを紛らわすことができるため、ストレスの軽減にもつながります。
・犬による性格や特徴の違いを楽しめる
たとえ同じ犬種だとしても、性格や成長具合はさまざま。異なる犬種であれば、さらに差がハッキリと見えてきます。
犬それぞれの違いを楽しめるのも、多頭飼いならではのメリットと言えるでしょう。
デメリット
・相性が悪いと喧嘩の原因になる
先住犬や新入り犬の性格がどうしても合わなかった場合、頻繁に喧嘩が起こることがあります。
この場合、それぞれの犬への接し方や、しつけの方法、居住スペースの位置を見直す必要があるでしょう。
・愛情の偏りが犬のストレスになる
1匹の犬だけを過剰にかわいがることは、ほかの犬に多大なストレスを与えます。
個体差によって見た目や性格に違いがでることは当たり前のことです。多頭飼いでは、どの犬にも平等に愛情を注ぐことが求められます。
先住犬や新入り犬の性格がどうしても合わなかった場合、頻繁に喧嘩が起こることがあります。
この場合、それぞれの犬への接し方や、しつけの方法、居住スペースの位置を見直す必要があるでしょう。
・愛情の偏りが犬のストレスになる
1匹の犬だけを過剰にかわいがることは、ほかの犬に多大なストレスを与えます。
個体差によって見た目や性格に違いがでることは当たり前のことです。多頭飼いでは、どの犬にも平等に愛情を注ぐことが求められます。
犬の多頭飼いに必要な準備

多頭飼いするときは、原則として1匹ごとに独立した居住スペースやトイレが必要になります。犬同士の性格や相性も考慮しながら、下記のような準備をしましょう。
ケージ、サークル
留守番のときや就寝時に使用するケージは、1匹ずつ別のものを用意しましょう。
家の中でサークルを使用する場合、犬の性格や相性を見極めたうえで問題がなければ1つのサークルでも大丈夫です。その場合、犬がそれぞれ自分のスペースをゆったり確保できるだけの広さが必要になります。
家の中でサークルを使用する場合、犬の性格や相性を見極めたうえで問題がなければ1つのサークルでも大丈夫です。その場合、犬がそれぞれ自分のスペースをゆったり確保できるだけの広さが必要になります。
ベッド
犬にとってのベッドとは、快適に安心して眠れる大事な場所。犬ごとに自分の匂いがついた専用のベッドが必要です。
それぞれのケージやサークルの中で、犬が安心できる場所に設置しましょう。
それぞれのケージやサークルの中で、犬が安心できる場所に設置しましょう。
クレート
犬との外出時や就寝時にも使えるクレートも、1匹につき1つずつ必要になります。それぞれ犬の大きさに合ったサイズを選びましょう。
トイレ
トイレも1匹につき1つずつ用意するのが原則です。複数の犬でトイレを共有する場合もありますが、犬の性格や相性によるところが大きいでしょう。
同じサークル内で多頭飼いしている場合も、できる限り離れた場所にそれぞれのトイレを設置しましょう。
同じサークル内で多頭飼いしている場合も、できる限り離れた場所にそれぞれのトイレを設置しましょう。
犬を多頭飼いするときの注意点

多頭飼いを成功させるためには、飼い主がいくつかのルールを守る必要があります。特に気を付けておくべき注意点を、事前にチェックしましょう。
ごはんを与える順番は?
毎食、同じ順番でごはんを与えるのがルールです。
どの犬を最初にするのかは、「犬同士が決めた序列の上位から」が基本。先住犬と新入り犬の月齢が離れている場合は、先住犬の序列が上になることが多いとされますが、必ずしもそうでないパターンもあります。
犬同士の上下関係をしっかり守ってあげることも、群れのリーダーとしての飼い主に求められることの一つです。
どの犬を最初にするのかは、「犬同士が決めた序列の上位から」が基本。先住犬と新入り犬の月齢が離れている場合は、先住犬の序列が上になることが多いとされますが、必ずしもそうでないパターンもあります。
犬同士の上下関係をしっかり守ってあげることも、群れのリーダーとしての飼い主に求められることの一つです。
複数の犬を同時に散歩させても大丈夫?
原則として1匹ずつが望ましいですが、時間の関係で同時に散歩させたいこともあるでしょう。
それぞれの犬のしつけができており、成長具合が同じくらいの場合、犬同士の相性がよい場合は、2匹同時の散歩も可能です。
1本のリードが二股に分かれている専用グッズを使用すると、リード同士の絡まりが起きにくくなります。
複数で散歩するときは、あらかじめリードを付けて歩く練習を行い、近場から遠方へと徐々に距離に伸ばしていくといいでしょう。
成犬と子犬など体格の違う犬同士や、相性の悪い犬同士の場合では、足並みが揃わずかえって1匹ずつの散歩のほうが楽になることもあります。もちろん無理は禁物です。
それぞれの犬のしつけができており、成長具合が同じくらいの場合、犬同士の相性がよい場合は、2匹同時の散歩も可能です。
1本のリードが二股に分かれている専用グッズを使用すると、リード同士の絡まりが起きにくくなります。
複数で散歩するときは、あらかじめリードを付けて歩く練習を行い、近場から遠方へと徐々に距離に伸ばしていくといいでしょう。
成犬と子犬など体格の違う犬同士や、相性の悪い犬同士の場合では、足並みが揃わずかえって1匹ずつの散歩のほうが楽になることもあります。もちろん無理は禁物です。
喧嘩や過剰なじゃれあいをはじめたときはどうする?
じゃれ合いがエスカレートして喧嘩に発展し、けがの恐れがあるときは飼い主がストップをかけます。
犬のカーミングシグナルを見習い、無言で犬の間に体を割り込ませて制止します。そして犬が落ち着くのを待ち、引き離して様子を見ましょう。
喧嘩が絶えないようであれば、飼育環境やしつけを見直す必要があります。
犬のカーミングシグナルを見習い、無言で犬の間に体を割り込ませて制止します。そして犬が落ち着くのを待ち、引き離して様子を見ましょう。
喧嘩が絶えないようであれば、飼育環境やしつけを見直す必要があります。
犬の多頭飼いにおすすめの組合せ

多頭飼いを考えるうえで、犬同士の相性は特に重要です。比較的多頭飼いしやすいおすすめの組み合わせを紹介します。
同じ犬種同士
トイプードル同士、チワワ同士など、同じ犬種で揃えるパターンは比較的多頭飼いに向いています。
気質の差異が小さいほか、必要な運動量も近しいため、一緒にお散歩するときもペースが合います。
また、複数飼うことでその犬種に対する知識を深められるというメリットも。エサやおもちゃ、ケージのサイズも選びやすくなります。
気質の差異が小さいほか、必要な運動量も近しいため、一緒にお散歩するときもペースが合います。
また、複数飼うことでその犬種に対する知識を深められるというメリットも。エサやおもちゃ、ケージのサイズも選びやすくなります。
サイズ(体重)が近い犬同士
大型犬なら大型犬同士、小型犬なら小型犬同士と、似たようなサイズ感の犬同士で合わせることが望ましいです。
体のサイズが極端に違う犬を一緒に飼うと、じゃれ合いなどで小さいほうの犬が思わぬけがをする恐れがあります。
体のサイズが極端に違う犬を一緒に飼うと、じゃれ合いなどで小さいほうの犬が思わぬけがをする恐れがあります。
オスとメス、異なる性別の犬同士
気質に違いのあるオスとメス同士が最もよい組み合わせで、争いごとが起きにくいとされます。
近い月齢のオス同士の場合、順位付けや縄張り争いが起こりやすいです。
また、互いに干渉しない傾向があるとされるメス同士の場合でも、異性同士と比べると順位付けの争いが起こる可能性は高まります。
しかし、未去勢のオス・メスを一緒に飼うことは、繁殖の可能性があるとともに、犬にとっても大きな負担になります。それぞれの犬が去勢できる月齢になったら、早めに手術するようにしましょう。
近い月齢のオス同士の場合、順位付けや縄張り争いが起こりやすいです。
また、互いに干渉しない傾向があるとされるメス同士の場合でも、異性同士と比べると順位付けの争いが起こる可能性は高まります。
しかし、未去勢のオス・メスを一緒に飼うことは、繁殖の可能性があるとともに、犬にとっても大きな負担になります。それぞれの犬が去勢できる月齢になったら、早めに手術するようにしましょう。
犬の年齢を考慮した組み合わせ
新しく迎え入れるのが子犬で、先住犬も生後半年未満の場合は、きょうだい的な存在として一緒に育てるのがいいでしょう。可能であれば、きょうだいとして生まれ育った犬を同時に引き取るのがベストです。
また、先住犬が成犬の場合は、小型犬は2歳、大型犬は3歳頃からなど、心身ともに成熟し、落ち着きがでてくるタイミングで迎えるのよいです。この場合、先住犬は新しく迎える犬にとって上位の立ち位置になります。
逆に、先住犬が10歳を超えるシニア犬の場合は、新しい犬が増えることで環境が変わることが大きな負担になる恐れがあります。
また、先住犬が成犬の場合は、小型犬は2歳、大型犬は3歳頃からなど、心身ともに成熟し、落ち着きがでてくるタイミングで迎えるのよいです。この場合、先住犬は新しく迎える犬にとって上位の立ち位置になります。
逆に、先住犬が10歳を超えるシニア犬の場合は、新しい犬が増えることで環境が変わることが大きな負担になる恐れがあります。
まとめ

以上が多頭飼いするうえでのメリットやデメリット、飼育のポイントに関する解説でした。
犬飼いなら一度は憧れる人も多いであろう多頭飼い。たくさんの犬と生活することは喜びが大きい反面、苦労も多くなるものです。
まずは今の環境で問題がないか十分に検討を重ねたうえで、多頭飼いの準備を進めましょう。
犬飼いなら一度は憧れる人も多いであろう多頭飼い。たくさんの犬と生活することは喜びが大きい反面、苦労も多くなるものです。
まずは今の環境で問題がないか十分に検討を重ねたうえで、多頭飼いの準備を進めましょう。
執筆者プロフィール
『みんなのペットライフ』編集部スタッフが、わんちゃん・ねこちゃんの飼い方、しつけのアドバイスなど、毎日のペットライフに役立つ知識や情報をお届けします。
犬のブリーダーについて

魅力たっぷりの犬をあなたも迎えてみませんか?
おすすめは、ブリーダーとお客様を直接つなぐマッチングサイトです。国内最大のブリーダーズサイト「みんなのブリーダー」なら、優良ブリーダーから健康的な子犬を迎えることができます。
いつでもどこでも自分のペースで探せるのがインターネットの魅力。「みんなのブリーダー」では写真や動画、地域などさまざまな条件で理想の犬を探せるほか、多数の成約者の口コミが揃っています。気になる方はぜひ参考にしてみてくださいね。
※みんなのブリーダーに移動します