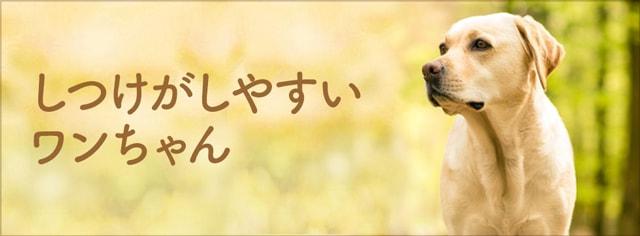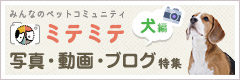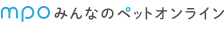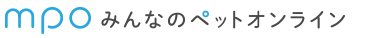ペットが亡くなったら…①安置、納棺

死後硬直とは
犬は亡くなると、多くの動物と同じように、死後硬直が起こります。
死後硬直とは、筋肉や関節が硬化する現象をいいます。犬の場合はだいたい死後2~3時間で始まるといわれており、硬直は手足から腹部、頭部へと広がっていきます。
死後硬直とは、筋肉や関節が硬化する現象をいいます。犬の場合はだいたい死後2~3時間で始まるといわれており、硬直は手足から腹部、頭部へと広がっていきます。
死後硬直の前にお清め
愛犬が亡くなったら、死後硬直が始まる前にお清めを行いましょう。
いつものブラシで丁寧に毛並みを整え、開いている場合は目と口を閉じてあげます。
目は手を添えて閉じさせるのですが、スムーズに閉じない場合がほとんどです。その際は強い力を使ったり、無理矢理したりしないようにしましょう。閉じなければそのままで構いません。
次に、お湯で湿らせた布で、お顔まわりと全身をやさしく拭き、尻尾を整えます。
愛犬の手足がピンと伸びていると、棺におさまらない場合があります。硬直が始まる前に、両手足の関節をゆっくり胸のほうへ折り曲げてください。
お清め中、口や肛門から体液が滲み出ることがあります。ガーゼなどで拭き取りましょう。排せつ物が出てくる可能性もありますが、死後硬直が始まれば次第におさまります。
いつものブラシで丁寧に毛並みを整え、開いている場合は目と口を閉じてあげます。
目は手を添えて閉じさせるのですが、スムーズに閉じない場合がほとんどです。その際は強い力を使ったり、無理矢理したりしないようにしましょう。閉じなければそのままで構いません。
次に、お湯で湿らせた布で、お顔まわりと全身をやさしく拭き、尻尾を整えます。
愛犬の手足がピンと伸びていると、棺におさまらない場合があります。硬直が始まる前に、両手足の関節をゆっくり胸のほうへ折り曲げてください。
お清め中、口や肛門から体液が滲み出ることがあります。ガーゼなどで拭き取りましょう。排せつ物が出てくる可能性もありますが、死後硬直が始まれば次第におさまります。
棺桶に適しているもの
素材は段ボール、合板、桐、また、おくるみのような形状をした布製、カゴ型のやなぎ製の棺などがあります。
しかし、これらの素材は火葬の一緒に入れられないことが多いので注意しましょう。
理由は、燃えるものの灰が多く出る、逆に燃えにくいなど、お骨に影響を与える可能性があるためです。火葬の際に棺から出して、遺体と副葬品を火葬するという業者もあるようです。
火力の問題もあり、細かな規定は施設それぞれ違いますので、問い合わせの際に確認してみましょう。
しかし、これらの素材は火葬の一緒に入れられないことが多いので注意しましょう。
理由は、燃えるものの灰が多く出る、逆に燃えにくいなど、お骨に影響を与える可能性があるためです。火葬の際に棺から出して、遺体と副葬品を火葬するという業者もあるようです。
火力の問題もあり、細かな規定は施設それぞれ違いますので、問い合わせの際に確認してみましょう。
安置、納棺の方法
愛犬の体が入るサイズの箱やカゴを用意しましょう。体液がしみ出すことがありますので、一番下にビニールやトイレシートを敷きましょう。
次に、愛犬が愛用していた毛布やタオルを敷きます。
腐敗の進行を遅らせる必要があれば、保冷剤を入れます。頭とお腹部分には多めに置いてください。
最後に、愛犬の体をバスタオルなどで包み込むようにすると、保冷性が高まります。
次に、愛犬が愛用していた毛布やタオルを敷きます。
腐敗の進行を遅らせる必要があれば、保冷剤を入れます。頭とお腹部分には多めに置いてください。
最後に、愛犬の体をバスタオルなどで包み込むようにすると、保冷性が高まります。
ペットが亡くなったら…②供養

ペットの安置、納棺が済んだら供養について考えましょう。ペットの場合は埋葬か火葬か選ぶことができます。
埋葬
埋葬とは「遺体を土に埋めること」つまり土葬のことです。遺体をそのまま埋める方法と火葬後に遺骨を埋める方法があります。
お骨や遺体を、公共の場や他人の土地に埋めることはできません。自宅の庭など私有地であれば埋葬は可能ですが、将来、売却や譲渡などで他人の手に渡る場合もありますので、あらゆる可能性を考えて決めましょう。
埋葬すると決めたら
まずは場所を決め、穴を掘ります。火葬のあとのお骨埋葬でしたら、深さ30cmくらいを目安に掘るといいでしょう。お骨を骨壺から取り出し、ガーゼなどの布で包んで埋葬します。
遺体をそのまま埋める(土葬)場合は、埋める場所が浅いと、カラスなどに遺体の臭いを嗅ぎつけられ掘り返されてしまうおそれがあります。深さは1m以上が望ましいです。遺体は綿やシルクなど天然素材の布で包みます。ポリエステルなど化学繊維は土に還りにくいため、使用しないようにしましょう。
お骨や遺体を、公共の場や他人の土地に埋めることはできません。自宅の庭など私有地であれば埋葬は可能ですが、将来、売却や譲渡などで他人の手に渡る場合もありますので、あらゆる可能性を考えて決めましょう。
埋葬すると決めたら
まずは場所を決め、穴を掘ります。火葬のあとのお骨埋葬でしたら、深さ30cmくらいを目安に掘るといいでしょう。お骨を骨壺から取り出し、ガーゼなどの布で包んで埋葬します。
遺体をそのまま埋める(土葬)場合は、埋める場所が浅いと、カラスなどに遺体の臭いを嗅ぎつけられ掘り返されてしまうおそれがあります。深さは1m以上が望ましいです。遺体は綿やシルクなど天然素材の布で包みます。ポリエステルなど化学繊維は土に還りにくいため、使用しないようにしましょう。
火葬
火葬とは「遺体を焼き、残った骨を葬ること」です。人の供養の際にも行われている方法です。
現在、多くのペット専用葬儀社があり、さまざまなサービスが用意されています。
火葬からお骨上げまで立ち合いが可能なところ、遺骨の返還、手元供養や分骨が可能なところなど実にさまざまです。料金も葬儀社によって異なりますので、納得いくまで調べてみましょう。
また、昨今では、住民のペット焼却を引き受けてくれる自治体も増えてきました。
民間の葬儀社と比較して費用がおさえられる点がメリットです。個別火葬や遺骨の返還が可能な自治体も、少しずつですが増えてきています。後悔しないようにしっかり考えて決めましょう。
現在、多くのペット専用葬儀社があり、さまざまなサービスが用意されています。
火葬からお骨上げまで立ち合いが可能なところ、遺骨の返還、手元供養や分骨が可能なところなど実にさまざまです。料金も葬儀社によって異なりますので、納得いくまで調べてみましょう。
また、昨今では、住民のペット焼却を引き受けてくれる自治体も増えてきました。
民間の葬儀社と比較して費用がおさえられる点がメリットです。個別火葬や遺骨の返還が可能な自治体も、少しずつですが増えてきています。後悔しないようにしっかり考えて決めましょう。
供養
供養の方法はは大きく分けて二つあります。一つは納骨堂や霊園などに納骨し供養する方法、もう一つはお骨を自宅等身近に置き供養する手元供養です。
霊園は、人間の霊園にペット霊園を併設しているところや、お寺が運営している霊園などもあります。合同墓と個別墓があり、霊園によっては定期的に大きな法要を行っています。
お骨を自宅など身近な場所に保管する手元供養には、特にしきたりはありません。
仏壇スペースをつくり、お線香をあげたりお花を供えたり、分骨しキーホルダーにして持ち歩いたり、飼い主さんご自身が納得できる、自分なりの供養が可能です。ペット用仏具も多くの種類が販売されています。
霊園は、人間の霊園にペット霊園を併設しているところや、お寺が運営している霊園などもあります。合同墓と個別墓があり、霊園によっては定期的に大きな法要を行っています。
お骨を自宅など身近な場所に保管する手元供養には、特にしきたりはありません。
仏壇スペースをつくり、お線香をあげたりお花を供えたり、分骨しキーホルダーにして持ち歩いたり、飼い主さんご自身が納得できる、自分なりの供養が可能です。ペット用仏具も多くの種類が販売されています。
ペットが亡くなったら…③手続き

愛犬が亡くなると、納棺や火葬などお別れの手配で精一杯で、しばらくは何もしたくない状態になってしまう方がほとんどだと思います。
しかし、狂犬病予防法の観点から、犬が死亡した場合には自治体への30日以内の死亡届け提出が義務づけられています。
鑑札や注射済票の返還が必要な場合もありますので、連絡をしてみましょう。
ペット保険に加入している方は、解約手続きが必要です。
血統書や発行されている場合は、血統書団体への届け出が必要なケースもあります。
しかし、狂犬病予防法の観点から、犬が死亡した場合には自治体への30日以内の死亡届け提出が義務づけられています。
鑑札や注射済票の返還が必要な場合もありますので、連絡をしてみましょう。
ペット保険に加入している方は、解約手続きが必要です。
血統書や発行されている場合は、血統書団体への届け出が必要なケースもあります。
ペットが亡くなったら…④ペットロス

もし、最期の瞬間をそばで過ごすことができたなら、これまでの思い出、感謝の気持ち、労いの言葉などを愛犬に伝えてみましょう。
最期の瞬間に伝えられなければ、火葬の前でもいいですし、思いを文字にし、棺にお手紙を入れるのもいい方法です。
愛犬とのお別れは耐え難いものですが、感謝の意持ちを伝えることができれば、いくらか心は救われます。
最期の瞬間に伝えられなければ、火葬の前でもいいですし、思いを文字にし、棺にお手紙を入れるのもいい方法です。
愛犬とのお別れは耐え難いものですが、感謝の意持ちを伝えることができれば、いくらか心は救われます。
ペットロスの症状
・突然悲しくなり、涙が出る
・無気力、虚無感
・疲労感、疲れやすい
・楽しい、嬉しいという感情が持てない
・眠れない、食欲がない
・吐き気、めまい、胃痛、頭痛、発熱など
これらの症状は時間が経つにつれ軽くなっていきます。悪化したり、長引いたりした場合は、親しい友人やペットロス専門のカウンセラーに相談されることをおすすめします。
・無気力、虚無感
・疲労感、疲れやすい
・楽しい、嬉しいという感情が持てない
・眠れない、食欲がない
・吐き気、めまい、胃痛、頭痛、発熱など
これらの症状は時間が経つにつれ軽くなっていきます。悪化したり、長引いたりした場合は、親しい友人やペットロス専門のカウンセラーに相談されることをおすすめします。
乗り越える方法
悲しみを解放させる
悲しみから逃れようと感情に蓋をしたり、無理に忙しくして気を紛らわせようとしたりせず、泣きたいときは思いっきり泣きましょう。
愛犬に手紙を書く、誰かに話を聞いてもらう
初七日、四十九日、月命日などのタイミングで、愛犬に手紙を書いてみましょう。
手紙を書くことで混乱した感情を整理できます。後悔や悲しみを文字にし、気持ちを整理できれば、愛犬が亡くなったという理不尽な現実をゆっくりと受け入れられるようになるはずです。
撮りためていた写真や動画を見たり、アルバム作りをしたりして、思い出を整理するのも有効な作業です。
誰かに話を聞いてもらうのも、ペットロスを乗り越えるのに効果的な方法です。身内や親しい犬友達ではなく、あえてSNSで出会った犬友達や、初対面の人に頼るという方法もあります。愛犬との思い出話を聞いてもらいましょう。
悲しみから逃れようと感情に蓋をしたり、無理に忙しくして気を紛らわせようとしたりせず、泣きたいときは思いっきり泣きましょう。
愛犬に手紙を書く、誰かに話を聞いてもらう
初七日、四十九日、月命日などのタイミングで、愛犬に手紙を書いてみましょう。
手紙を書くことで混乱した感情を整理できます。後悔や悲しみを文字にし、気持ちを整理できれば、愛犬が亡くなったという理不尽な現実をゆっくりと受け入れられるようになるはずです。
撮りためていた写真や動画を見たり、アルバム作りをしたりして、思い出を整理するのも有効な作業です。
誰かに話を聞いてもらうのも、ペットロスを乗り越えるのに効果的な方法です。身内や親しい犬友達ではなく、あえてSNSで出会った犬友達や、初対面の人に頼るという方法もあります。愛犬との思い出話を聞いてもらいましょう。
友人がペットロスになっている場合
友人との間柄、状況などで適切な言葉は違いますが、言ってはいけない言葉は共通です。
例えば「かわいそうに」「まだ若かったよね」などの言葉や、「そんなに泣いていたら〇〇ちゃん(亡くなったペット)が悲しむよ」のような、飼い主さんの悲しみを否定する言葉は言ってはいけません。
過度ではない自然な励ましができれば良いですが、実は話を聞いてあげるだけでも十分という場合も多いのです。お花を供えに行くのもいいでしょう。
例えば「かわいそうに」「まだ若かったよね」などの言葉や、「そんなに泣いていたら〇〇ちゃん(亡くなったペット)が悲しむよ」のような、飼い主さんの悲しみを否定する言葉は言ってはいけません。
過度ではない自然な励ましができれば良いですが、実は話を聞いてあげるだけでも十分という場合も多いのです。お花を供えに行くのもいいでしょう。

ありったけの愛情を注ぎ、できる限りのお世話をしてきても、後悔はつきものです。後悔は、悲しみをさらに強めるのかもしれません。
けれども、後悔は正常な感情です。ペットロスは当たり前の反応だと知っておくのは、必要以上の悲しみを背負わないために大切な知識となるでしょう。
けれども、後悔は正常な感情です。ペットロスは当たり前の反応だと知っておくのは、必要以上の悲しみを背負わないために大切な知識となるでしょう。
執筆者プロフィール
犬のブリーダーについて

魅力たっぷりの犬をあなたも迎えてみませんか?
おすすめは、ブリーダーとお客様を直接つなぐマッチングサイトです。国内最大のブリーダーズサイト「みんなのブリーダー」なら、優良ブリーダーから健康的な子犬を迎えることができます。
いつでもどこでも自分のペースで探せるのがインターネットの魅力。「みんなのブリーダー」では写真や動画、地域などさまざまな条件で理想の犬を探せるほか、多数の成約者の口コミが揃っています。気になる方はぜひ参考にしてみてくださいね。
※みんなのブリーダーに移動します