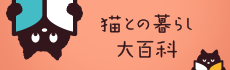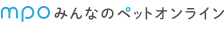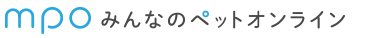猫もフィラリア症にかかる

猫のフィラリア症は、犬同様フィラリアの子虫を持った蚊にさされることで感染します。体内に入った虫が血流に乗って心臓や肺に寄生・増殖し、心・肺疾患や、猫では急性のアレルギーを引き起こす病気です。
フィラリアは、日本語では「犬糸状虫」というぐらいなので、本来は犬を宿主とする寄生虫です。この「宿主」というのは、「虫が住みつく→成虫になる→卵を産む→成虫になる→繁殖する」という「生活環」を営める動物のことです。
猫は、犬糸状虫の宿主ではないため、フィラリアがこの生活環を維持することが難しく、厳密には「寄生」されることは少ないです。しかし「感染」することは可能です。
犬ほどではなくても、感染すると体内ではフィラリアが増殖し、愛猫の体に異常をきたします。また寄生が成立しにくい分、「迷入」といって、本来寄生する部位(フィラリアであれば心臓の肺動脈)とは別の部位でフィラリアが増殖してしまうことが、猫では多く起こります。
フィラリアは、日本語では「犬糸状虫」というぐらいなので、本来は犬を宿主とする寄生虫です。この「宿主」というのは、「虫が住みつく→成虫になる→卵を産む→成虫になる→繁殖する」という「生活環」を営める動物のことです。
猫は、犬糸状虫の宿主ではないため、フィラリアがこの生活環を維持することが難しく、厳密には「寄生」されることは少ないです。しかし「感染」することは可能です。
犬ほどではなくても、感染すると体内ではフィラリアが増殖し、愛猫の体に異常をきたします。また寄生が成立しにくい分、「迷入」といって、本来寄生する部位(フィラリアであれば心臓の肺動脈)とは別の部位でフィラリアが増殖してしまうことが、猫では多く起こります。
猫の感染率
猫の感染率は、同じ地域に住んでいる犬のフィラリア感染率に対して5~20%と言われています。つまり、ご近所一帯の犬100頭を調べて10頭フィラリアに感染していたとしたら、同じ区域で0~2匹の猫がフィラリアに感染している可能性があるということです。
しかし実際には、犬を100頭中10頭も感染している地域は少なく、猫の感染はごくまれにはなります。しかし、犬のフィラリアの発症が多い地域では、当然ながら感染の警戒が必要になります。
しかし実際には、犬を100頭中10頭も感染している地域は少なく、猫の感染はごくまれにはなります。しかし、犬のフィラリアの発症が多い地域では、当然ながら感染の警戒が必要になります。
猫がフィラリア症にかかるとどうなる?

感染すると元気や食欲低下、嘔吐、急な咳などが起こります。感染後、一時的に起こり、しばらくすると症状がなくなってしまうこともあります。咳がもっとも多くみられる症状ですが、一定ではありません。無症状の猫もいれば、継続的な嘔吐が唯一の症状のこともあります。
感染5~6カ月頃に、子虫が心臓に達します。これにより血栓塞栓(血管が詰まること)や、急性の呼吸困難(肺の炎症による変化やアレルギー反応による)、失神など、重篤な症状が現れることが多くなります。
春の感染が多いため、症状が出てフィラリア症が疑われるようになるのは、秋~冬が多いです。激烈な症状からは、回復する場合もありますが、突然死に至るケースもあります。猫は犬に比べて体が小さい分、血栓塞栓による突然死のリスクは高いと言われています。
ほかに、心臓以外の場所にフィラリアが住んでしまう「迷入」は、脳に多いです。この場合、けいれんや神経症状が、突然起こります。咳などの心肺症状と神経症状が、同時に起こることはまれです。フィラリア症の主な症状である発咳は、アレルギーや気管支炎、フィラリア以外の心臓病でも起こります。
フィラリア症か否かの診断は、胸部のレントゲンと血液検査などで判断します。ただし、犬より判断は難しく、診断がつかないこともあります。血液の検査は、フィラリアに含まれる物質を調べる、抗原検査を行います。
しかし、猫の体内ではフィラリアの数が増えにくいため、抗原数が少なく、検査で発見できないことも多いです。
感染5~6カ月頃に、子虫が心臓に達します。これにより血栓塞栓(血管が詰まること)や、急性の呼吸困難(肺の炎症による変化やアレルギー反応による)、失神など、重篤な症状が現れることが多くなります。
春の感染が多いため、症状が出てフィラリア症が疑われるようになるのは、秋~冬が多いです。激烈な症状からは、回復する場合もありますが、突然死に至るケースもあります。猫は犬に比べて体が小さい分、血栓塞栓による突然死のリスクは高いと言われています。
ほかに、心臓以外の場所にフィラリアが住んでしまう「迷入」は、脳に多いです。この場合、けいれんや神経症状が、突然起こります。咳などの心肺症状と神経症状が、同時に起こることはまれです。フィラリア症の主な症状である発咳は、アレルギーや気管支炎、フィラリア以外の心臓病でも起こります。
フィラリア症か否かの診断は、胸部のレントゲンと血液検査などで判断します。ただし、犬より判断は難しく、診断がつかないこともあります。血液の検査は、フィラリアに含まれる物質を調べる、抗原検査を行います。
しかし、猫の体内ではフィラリアの数が増えにくいため、抗原数が少なく、検査で発見できないことも多いです。
もし愛猫がフィラリア症と診断されたら

上記でも触れたように、猫の体内は、フィラリアにとって育ちにくい環境です。感染した幼虫が成虫まで成熟することは少なく、さらに成虫の寿命が短くなります。これは、無治療の状態でもフィラリアが増殖しにくく、フィラリアが自然と死滅する可能性がある、ということを指します。
また犬で使われる治療薬は、猫では突然死など、重い合併症を招く危険性が高いと言われています。
そのため、明らかな呼吸症状がない場合は、フィラリアを積極的に死滅させる治療薬は使わず、ステロイドで異物による炎症反応を抑えながら、経過をみていく保存療法が選ばれることがあります。病気の経過を把握するためには、半年に1回程度の胸部のレントゲン撮影がすすめられます。
治療費はステロイドの飲み薬代が主となり、その都度、愛猫の状態に合わせて変動していく形になります。ただし、経過をしっかりと見ていても、虫体が自然死したあとには、重い呼吸困難が急に起こったり、最悪突然死したりすることもあります。
フィラリア感染による呼吸症状が認められる場合は、まず投薬による症状の改善治療が行われます。心臓や肺への負荷がある程度改善されれば、数週間のケージ内での生活による安静後、フィラリアを積極的に死滅される治療薬の使用が、順に行われます。
これらの治療の場合、愛猫の状態の改善にある程度の費用が必要であり、フィラリア治療薬(注射)自体は数千円になります。
どちらの場合も、虫体が駆除されるまでには、1年以上かかることがあります。
また犬で使われる治療薬は、猫では突然死など、重い合併症を招く危険性が高いと言われています。
そのため、明らかな呼吸症状がない場合は、フィラリアを積極的に死滅させる治療薬は使わず、ステロイドで異物による炎症反応を抑えながら、経過をみていく保存療法が選ばれることがあります。病気の経過を把握するためには、半年に1回程度の胸部のレントゲン撮影がすすめられます。
治療費はステロイドの飲み薬代が主となり、その都度、愛猫の状態に合わせて変動していく形になります。ただし、経過をしっかりと見ていても、虫体が自然死したあとには、重い呼吸困難が急に起こったり、最悪突然死したりすることもあります。
フィラリア感染による呼吸症状が認められる場合は、まず投薬による症状の改善治療が行われます。心臓や肺への負荷がある程度改善されれば、数週間のケージ内での生活による安静後、フィラリアを積極的に死滅される治療薬の使用が、順に行われます。
これらの治療の場合、愛猫の状態の改善にある程度の費用が必要であり、フィラリア治療薬(注射)自体は数千円になります。
どちらの場合も、虫体が駆除されるまでには、1年以上かかることがあります。
猫のフィラリア症は予防が大切

そもそも、猫はフィラリアにかかっているという診断が難しく、生きている間に確定診断はできないとまで言われています。そのため、治療は困難を極めることもあります。
したがって、犬でのフィラリア感染が多い地域では、猫でも予防薬を投与することが強くすすめられます。
猫への感染は、犬の体内で育った感染子虫(ミクロフィラリア)が、吸血により体内に取り込まれ、その蚊がまた猫を刺すことで起こります。このため、予防期間としては「蚊が活動し始めて1カ月後~活動が終わる1カ月後」、毎月1回の投薬が目安になります。犬の予防期間と同じです。
フィラリアの予防薬は、「予防」という名を冠しますが、実際には「駆除」に近く、体内にフィラリアが取り込まれるのを防ぐことはできません。体内のフィラリアを、成長段階で殺す作用を持ちます。
たとえば8月1日にフィラリア予防薬を飲んだとしましょう。その薬は、8月に蚊からフィラリアが移らないように愛猫を守っているのではなく、7月に体内に入ってしまったフィラリアを殺す役割を持っています。したがって、蚊が増え始める時期よりも、シーズン後半の投薬が重要になります。
猫の場合は、家からまったく出さないという飼い主も多くいるでしょう。しかし、家内に蚊が入ってくることを、完全に防ぐことはできません。たとえ完全室内飼いでも、予防は必要になります。
現在猫用に販売されているフィラリア予防薬は、チュアブルタイプもありますが、スポットタイプ(滴下式)が主流です。フィラリアだけでなく、ノミや消化管内寄生虫も駆除してくれるタイプがほとんどです。要指示薬のため、獣医師の処方箋が必要になり、動物病院でのみ取り扱われます。
スポットタイプは首のうしろの1~2か所に垂らして投薬します。同居の猫がいる場合は、吸収されるまでの1日程度、滴下部を舐めないように注意してあげてください。万一舐めても、中毒を起こすことはまれですが、薬剤の味により、よだれがひどくなることがあります。
したがって、犬でのフィラリア感染が多い地域では、猫でも予防薬を投与することが強くすすめられます。
猫への感染は、犬の体内で育った感染子虫(ミクロフィラリア)が、吸血により体内に取り込まれ、その蚊がまた猫を刺すことで起こります。このため、予防期間としては「蚊が活動し始めて1カ月後~活動が終わる1カ月後」、毎月1回の投薬が目安になります。犬の予防期間と同じです。
フィラリアの予防薬は、「予防」という名を冠しますが、実際には「駆除」に近く、体内にフィラリアが取り込まれるのを防ぐことはできません。体内のフィラリアを、成長段階で殺す作用を持ちます。
たとえば8月1日にフィラリア予防薬を飲んだとしましょう。その薬は、8月に蚊からフィラリアが移らないように愛猫を守っているのではなく、7月に体内に入ってしまったフィラリアを殺す役割を持っています。したがって、蚊が増え始める時期よりも、シーズン後半の投薬が重要になります。
猫の場合は、家からまったく出さないという飼い主も多くいるでしょう。しかし、家内に蚊が入ってくることを、完全に防ぐことはできません。たとえ完全室内飼いでも、予防は必要になります。
現在猫用に販売されているフィラリア予防薬は、チュアブルタイプもありますが、スポットタイプ(滴下式)が主流です。フィラリアだけでなく、ノミや消化管内寄生虫も駆除してくれるタイプがほとんどです。要指示薬のため、獣医師の処方箋が必要になり、動物病院でのみ取り扱われます。
スポットタイプは首のうしろの1~2か所に垂らして投薬します。同居の猫がいる場合は、吸収されるまでの1日程度、滴下部を舐めないように注意してあげてください。万一舐めても、中毒を起こすことはまれですが、薬剤の味により、よだれがひどくなることがあります。
まとめ

猫では、まだフィラリア予防を行っていない飼い主様が多いのが現状です。猫への感染は少ないものの、フィラリアに感染する犬がまだ見られる以上、油断はできません。
近年は、スポットタイプで簡単に予防できる薬が発売されていますので、ぜひ愛猫のフィラリア予防をしてくださいね。
近年は、スポットタイプで簡単に予防できる薬が発売されていますので、ぜひ愛猫のフィラリア予防をしてくださいね。
執筆者プロフィール
猫のブリーダーについて

魅力たっぷりの猫をあなたも迎えてみませんか?
おすすめは、ブリーダーとお客様を直接つなぐマッチングサイトです。国内最大のブリーダーズサイト「みんなの子猫ブリーダー」なら、優良ブリーダーから健康的な子猫を迎えることができます。
いつでもどこでも自分のペースで探せるのがインターネットの魅力。「みんなの子猫ブリーダー」では写真や動画、地域などさまざまな条件で理想の猫を探せるほか、多数の成約者の口コミが揃っています。気になる方はぜひ参考にしてみてくださいね。
※みんなの子猫ブリーダーに移動します