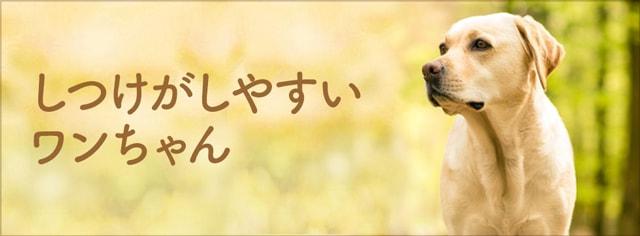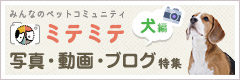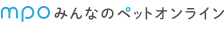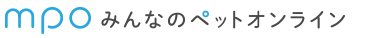子犬から老犬まで。ライフステージ別「散歩の目的」
「子犬」の散歩は社会経験を積む場

この時期の散歩は「さまざまな経験を通じて、人間社会に犬を慣らす」ことが大きな目的になります。
犬は小さな頃から外の刺激に敏感で、見知らぬ人やものに対して、恐怖心や警戒心を抱くことが多々あります。
散歩デビューする前の子犬は家族や家以外のことを知りません。子犬のうちに、家族以外の人やペット、電車や車の走行音など、外のあらゆる刺激に触れさせましょう。社会経験を積み重ねることで、多少のことでは動じない、問題行動の少ない犬に育っていきます。
「成犬」の散歩はコミュニケーション

いつもと同じルートを繰り返すのではなく、毎回何かしら変化をつけてあげると、犬もいつも新鮮な気分で散歩が楽しめますよ。
散歩に変化を加えるなら
・ルートを変える
・散歩のルートに、公園など自由に走り回れる場所を入れて、思いっきり遊ばせる
※走らせるなら、コンクリートよりも足腰に負担がかからない土の上にしましょう
・知的な遊びを取り入れる(知的玩具でトレーニングを兼ねた遊びなど)
犬にとって、毎回散歩が楽しみになるような「楽しい体験」を重ねることを心がけてみてください。
「老犬」の散歩は、スローペースで

・疲れやすい
・筋力が落ちる
・視力や聴覚が低下する
・骨がもろくなる
・気力が低下する
心身ともに老化の影響が出てくるので、散歩も犬に無理のない内容に変えていきましょう。元気な老犬であれば、運動量を急に減らす必要はありません。衰えが見えてきたら時間を短くしたり、坂道や階段を避けるルートを選ぶなど、工夫してあげてください。
部屋にこもりがちになると、ストレスが溜まる、気分が内向きになる、運動不足から肥満になるなど悪循環にもなります。毎日でなくても良いので、気分転換できるよう外へ誘い出しましょう。
「介護犬」は外に出ることを目的に
ハーネスで補助すれば歩ける、カートに乗せれば歩けるなど犬によって必要な補助は異なります。犬に合わせた補助をしながら外へ出て、気分転換させてあげましょう。
大型犬の場合は飼い主の負担も大きくなりますが、可能な範囲で散歩を続けてみてくださいね。
「嗅ぎたい」欲を満たす! 散歩のもうひとつの目的

犬の生活において「匂いを嗅ぐ」ことは情報収集やコミュニケーションのひとつ。社交的で外出が好きな犬にとって、散歩はさまざまな匂いに出会うことができる楽しい時間なのです。
犬が「嗅ぐ」意味
・挨拶
・自分の存在を主張する
・縄張りを確認する
・犬同士の親密さを確認する
天候不良などで外を歩けない日でも、ドッグカフェ、ドッグランなど「ペット連れOK」の場所に出かけて、犬の好奇心や本能を満たしてあげてください。多くの体験を重ねることで、社会に適応した成熟した犬になっていきます。
【散歩嫌いには】体調不良? 恐怖心? その理由を探ろう

体の不調、恐怖心、運動量が合わない(散歩は疲れると感じている)など、犬が嫌がる背景には必ず理由があります。犬が散歩を嫌がる原因についてよく考えてみましょう。
体の不調
◇フローリングの家は脱臼に注意
掃除もしやすく衛生的なことから、住宅でも広く用いられるフローリングですが、すべりやすいので、転倒など足を痛める原因にもなります。フロアマットを敷くなど、未然に怪我を防ぐ対処をしておけるといいですね。
恐怖心

特に子犬に多く、社会経験が不足しているとちょっとした刺激にも過敏に反応します。恐怖心を取り除くには、外の世界との接触を増やして社会性を養うことが大切です。
無理やり連れていくと、恐怖心を増長させるだけなので、段階的に慣れさせましょう。
まず、犬が安心できるよう、抱っこしたままの状態で外に出かけてみましょう。家の庭や近くの公園など、近場で構いません。そこで、おやつを与えたり、一緒に遊んで、犬にとって「楽しい」と感じる体験を増やしていきます。
ポジティブな体験を積み重ねることで恐怖心が減り、「外へ出ると楽しいことがある」と少しずつ外に興味を持つようになるでしょう。
犬と歩調を合わせよう

どちらかが引っ張っているような状態は望ましくありません。その場合、リードはピンと張った状態になります。
飼い主が持っているリードにゆとりがあれば、歩調はある程度合っていると見てよいでしょう。
◇リードの持ち方
片手でリードの持ち手を持ったら、もう片方の手でリードの中間付近を持ってください。歩くときは、リードに少したるみを持たせた状態をキープしながら歩きましょう。リードに余裕がない状態だと犬の動きをコントロールができません。
◇歩き方
犬を飼い主の左側に立たせ、同じ歩調で歩きましょう。これは犬の身を危険から守るためです。
怖がりな犬であっても「頼れる飼い主がそばにいる」という安心感があれば、散歩の時間を楽しめるようになりますよ。
良くない例

犬が主導権を握っている状態です。そのままにしておくと、犬が自分をリーダーだと勘違いするために、コントロールが利かなくなるので、犬に引っ張られたら「リードを引っ張って止まる」を徹底しましょう。
◇飼い主が犬を引っ張る=犬に無理をさせている
「犬が遅いから……」と言って、引きずって歩くことは避けてください。犬にとって、散歩が辛く苦しいものになってしまいます。ペースダウンして、犬と歩調を合わせるようにしましょう。
知らないと大変! 散歩に出かける前に必要な準備

ワクチン接種
◇狂犬病予防接種
法律(動物愛護法)で義務付けられている「狂犬病予防接種」。一年に一度、必ず受けさせましょう。自治体の集合会場、もしくは動物病院で受けることができます。
初年度…生後91日から接種が義務付けられます。早めに受けさせましょう。
2年目以降…1年に1回ペースになります。毎年春頃になると、自治体から集合注射のお知らせが通知されます。(案内ハガキによる通知のほか、ホームページや広報誌など通知方法は自治体によって異なります)
狂犬病は、感染後、発症すると治療することができません。しかしながら、狂犬病は予防注射することで感染は防げなくても発症を予防することができます。このことから、飼い犬にしっかりと予防注射を受けさせることで犬を狂犬病から守ることはもちろん、飼い主自身や家族、近所の住人や他の動物への感染を防止できます。
このことから生後91日以上の犬には早く予防注射を受けさせ、その後は1年に1回(予防注射接種時期は4~6月)の予防注射で免疫を補強させましょう。狂犬病予防注射はお住まいの市区町村が行う集合注射、または動物病院で接種することができます。

狂犬病以外の予防接種は任意ですが、病気予防に効果的な方法なので接種が推奨されています。ただし、副作用のリスクもゼロではないため、獣医師さんとよく相談して受けると良いでしょう。
何種類のワクチンを受けるかの判断は、居住地やライフスタイルをよく考慮する必要があります。次のような場合、ワクチンを接種して病気への免疫力を高めておいた方が良いとされています。
・野良犬が多い地域に住んでいる
・ドッグランやペットホテルをよく利用し、不特定多数の犬と接触する機会が多い
・海外旅行をする
すべての動物で毎年のワクチン接種が必要というわけではありません。
ワクチンには,全部の動物に接種すべきコアワクチンと,感染のリスクに応じて接種するノンコアワクチンの2種類があります。
コアワクチンが対象とする病気には,犬では犬ジステンパー,犬パルボウイルス感染症,犬伝染性肝炎と狂犬病があり,猫では猫汎白血球減少症(猫のパルボウイルス感染症),猫ウイルス性鼻気管炎,猫カリシウイルス感染症があります。
主なノンコアワクチンの対象には,犬ではレプトスピラ病,パラインフルエンザウイルス感染症など,猫では猫白血病ウイルス感染症,猫免疫不全ウイルス感染症(猫エイズ),クラミドフィラ・フェリス感染症などがあります。
日本獣医学会「Q&A 犬猫のワクチンについて」より http://www.jsvetsci.jp/10_Q&A/v20160527.html
共立製薬株式会社「わんにゃん豆知識 > 感染症 > 犬編 第3回:怖い・犬の感染症(2)」より http://www.kyoritsuseiyaku.co.jp/owner/knowledge/disease/dog3/index.html
フィラリア予防

基本的にフィラリアは予防薬で防ぐことができますが、要指示薬になっているので、必ず獣医師から処方を受けてください。
フィラリアは寄生虫の一種です。フィラリアは心臓や肺動脈に寄生し、体長が30cmに達することもあります。フィラリアが寄生すると血液循環に障害を及ぼします。また、病気が進むと呼吸が苦しいといった症状がみられます。そして、肝臓や腎臓など侵され、最後は衰弱して死に至る怖い病気です。
検査をしてからでないと与えてはいけません
投与する前にはフィラリアに感染していないことを検査する必要があります。 すでにフィラリアに感染していた状態で予防薬を与えるとかえって大切なペットを死に至らしめることもあります。インターネットでフィラリアの薬を買ったり個人輸入して与えると大きな事故の原因となりますので必ず獣医師から処方を受けてください。
ノミ、ダニ対策
◇対策
・家の中の掃除をし、衛生的な生活環境を心がける
・ブラッシングで被毛についたノミ・ダニを物理的に取り除く
・投薬(駆除薬)
駆除薬はスポットタイプ、錠剤タイプ、スプレータイプなど多種多様に揃っています。獣医師によく相談してから選ぶようにしましょう。
アレルギー対策
花粉に限らず犬のアレルギーは皮膚に出ることが多いのが特徴です。やたらとかゆがる、皮膚に炎症が起きているなど、犬にアレルギーと思わしき症状が見受けられたら動物病院でアレルギー検査し、獣医師のアドバイスを受けることをおすすめします。
医薬品の購入について注意したいこと

情報収集も容易になったことから、個人輸入も広がりを見せていますが、なかには海外で販売されている薬を個人で購入する人もいるようです。これは「動物用医薬品の個人輸入」にあたりますが、無許可で個人輸入すると違法行為になる危険が潜んでいます。
個人で輸入される動物用医薬品、動物用医薬部外品、動物用医療機器及び動物用再生医療等製品(以下「動物用医薬品等」という。)は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律145号。以下「医薬品医療機器等法」という。)に基づく承認等を受けておらず、日本国内での販売・譲渡は禁止されています。
また、動物用医薬品及び動物用再生医療等製品について、医薬品医療機器等法に基づく製造販売業の許可を受けた者以外による輸入は原則として禁止されています。
以上の規定に基づき、個人で輸入される動物用医薬品等が医薬品医療機器等法上、適正に輸入・使用されるか否かを確認するため、輸入確認願の提出をお願いしています。
◇個人輸入の注意点
薬以外の製品でも注意が必要です。たとえば、海外のシャンプーに含まれている成分が日本で使用が禁止されていることも……。禁止成分を含む商品を輸入すると、そのつもりはなくても「違法な物を輸入した」と疑いがかけられる可能性もあります。
財務省(税関)、農林水産省、厚生労働省、経済産業省など、あらゆる機関が関わる輸入の手続きは非常に煩雑です。インターネットで海外品を購入する際は十分気をつけてください。
農林水産省「動物用医薬品」より http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/yakuzi/index.html
農林水産省「動物用医薬品等に該当するか否かの考え方」より http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/yakuzi/y_import/
Jetro「動物用医薬品の輸入手続き:日本」より https://www.jetro.go.jp/world/qa/04M-010753.html
国民生活センター「事例で学ぶインターネット取引 医薬品等の個人輸入」より http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201308_03.pdf
散歩は準備万端で安全に楽しく犬に合わせて

また、安心安全に散歩を楽しむためには病気の予防も欠かせません。かかりつけの動物病院を決めて、獣医師と相談しながら対策していきましょう。
犬のブリーダーについて

魅力たっぷりの犬をあなたも迎えてみませんか?
おすすめは、ブリーダーとお客様を直接つなぐマッチングサイトです。国内最大のブリーダーズサイト「みんなのブリーダー」なら、優良ブリーダーから健康的な子犬を迎えることができます。
いつでもどこでも自分のペースで探せるのがインターネットの魅力。「みんなのブリーダー」では写真や動画、地域などさまざまな条件で理想の犬を探せるほか、多数の成約者の口コミが揃っています。気になる方はぜひ参考にしてみてくださいね。