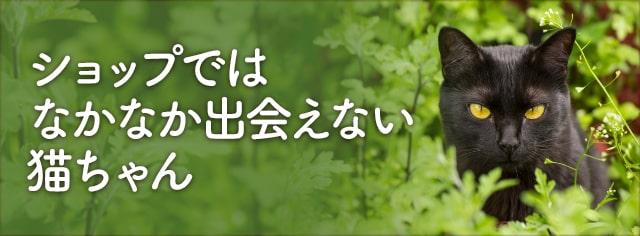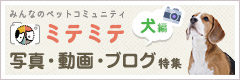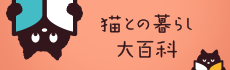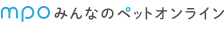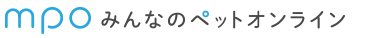目次
部屋で猫を飼うメリット

まず、猫を室内で飼うことによるメリットから確認していきましょう。
猫が安心する
猫は縄張りのなかで暮らす生き物。外敵のいない室内は、精神的安定をもたらす最高の縄張りとなります。
猫が安心できる空間を確保できるというのは、室内飼いの大きなメリットといえるでしょう。
猫が安心できる空間を確保できるというのは、室内飼いの大きなメリットといえるでしょう。
ほかの猫と争う心配がない
外で飼育した場合、飼い猫がほかの猫の縄張りに入り、ケンカになってしまうことがあります。
一度戦いになればケガをする可能性だけでなく、場合によっては命に関わります。相手が野良猫であれば、病気をもらってしまうリスクもあるでしょう。
また、争いに負けた猫は縄張りから追い出されるため、その範囲内に自宅がある場合には、飼い主の元に帰ってこなくなるということすら考えられます。
室内飼いであればほかの猫と接触する機会もないので、このような問題を心配する必要がありません。
一度戦いになればケガをする可能性だけでなく、場合によっては命に関わります。相手が野良猫であれば、病気をもらってしまうリスクもあるでしょう。
また、争いに負けた猫は縄張りから追い出されるため、その範囲内に自宅がある場合には、飼い主の元に帰ってこなくなるということすら考えられます。
室内飼いであればほかの猫と接触する機会もないので、このような問題を心配する必要がありません。
事故に遭う可能性がない
野良猫の死因の多くが交通事故だといわれています。これは猫の特性が関係しています。猫は引き返すことをしない生き物なので、一度道路に出ると、車がきても正面を突っ切ってしまうのです。車の大きな音や振動に立ちすくんで動けなくなった結果、轢かれてしまうというケースもあります。
また、猫はせまくて暗いところを好むので、車の下でくつろぐことが多いです。場合によってはエンジンルームに入り込む可能性さえあります。もしドライバーがこれに気付かず運転を始めてしまったら、大惨事になってしまうでしょう。
猫を完全室内飼いにすれば、これらの危険性をゼロにすることができます。
また、猫はせまくて暗いところを好むので、車の下でくつろぐことが多いです。場合によってはエンジンルームに入り込む可能性さえあります。もしドライバーがこれに気付かず運転を始めてしまったら、大惨事になってしまうでしょう。
猫を完全室内飼いにすれば、これらの危険性をゼロにすることができます。
病気や寄生虫の感染リスクが減る
外には病気や寄生虫を持っている生き物がたくさんいます。ネズミやカエルなどを捕食し、病気や寄生虫をもらってしまう可能性があります。なかには人にうつる病気もあるため、外に出さないことで飼い主の感染リスクを減らすことができます。
また、同じようにノミやダニからも身を守れるため、皮膚トラブルの回避にもつながります。
また、同じようにノミやダニからも身を守れるため、皮膚トラブルの回避にもつながります。
部屋で猫を飼うデメリット

次に、部屋で猫を飼うことのデメリットもチェックしていきましょう。
猫によってはストレスになる
外が好きな猫や、もともと野良だった猫を飼う場合には、外出できないことがストレスにつながる可能性があります。
ストレスがたまると問題行動や体調不良の原因になります。
このような事態を防ぐためにも、ストレスを発散できるような環境を室内につくってあげることが大切です。
ストレスがたまると問題行動や体調不良の原因になります。
このような事態を防ぐためにも、ストレスを発散できるような環境を室内につくってあげることが大切です。
室内ならではの事故
猫はさまざまなものに興味を持ちます。しかし、部屋の中には手を出しては危険なものもあります。
たとえば電気コードを噛んでしまえば感電の危険性がありますし、冬場はストーブに近づきすぎると火傷してしまうかもしれません。
また、人には無害でも猫にとっては毒となる食べ物もあります。基本的には、人の食べ物に猫を近づけないようにしましょう。
たとえば電気コードを噛んでしまえば感電の危険性がありますし、冬場はストーブに近づきすぎると火傷してしまうかもしれません。
また、人には無害でも猫にとっては毒となる食べ物もあります。基本的には、人の食べ物に猫を近づけないようにしましょう。
運動不足の可能性
部屋がせまいと、移動距離が小さくなるため、運動不足になる可能性があります。
運動不足は生活習慣病の原因になりますので、居住スペースがせまい方は、特に運動に気をつかってあげる必要があります。
ただ、これらのデメリットは飼い主の工夫次第で限りなく小さくすることが可能です。猫の性質と個性を把握し、飼い主も猫も住みやすい部屋づくりをしていきましょう。
運動不足は生活習慣病の原因になりますので、居住スペースがせまい方は、特に運動に気をつかってあげる必要があります。
ただ、これらのデメリットは飼い主の工夫次第で限りなく小さくすることが可能です。猫の性質と個性を把握し、飼い主も猫も住みやすい部屋づくりをしていきましょう。
猫のための部屋づくり ①猫が好む場所をつくる

猫は性質上、以下のような場所を好みます。意識して環境づくりをしてあげると喜んでくれるでしょう。
せまくて暗い場所
テレビや動画サイトなどで猫が段ボールに突っ込んでいったり、中でくつろいでいたりするのを見たことがあるでしょうか。
これは猫の先祖であるヤマネコが穴に住むネズミなどの獲物を探していたことや、せまくて暗い場所は獲物を安心して食べることができること、また、獲物の待ち伏せにも最適な場所だったことなどが理由に挙げられます。そ
の子孫である猫にもせまく、暗い場所と用意してあげると安心して過ごすことができます。
宅配便などで入手できる段ボールを利用すると、経済的かつ簡単です。
そのまま上面を開けた状態で使ってもいいですし、出入り口用の穴を開けても気に入ってくれるでしょう。
これは猫の先祖であるヤマネコが穴に住むネズミなどの獲物を探していたことや、せまくて暗い場所は獲物を安心して食べることができること、また、獲物の待ち伏せにも最適な場所だったことなどが理由に挙げられます。そ
の子孫である猫にもせまく、暗い場所と用意してあげると安心して過ごすことができます。
宅配便などで入手できる段ボールを利用すると、経済的かつ簡単です。
そのまま上面を開けた状態で使ってもいいですし、出入り口用の穴を開けても気に入ってくれるでしょう。
高い場所
猫は高いところも好みます。
これも外敵から身を守ったり、獲物を捕らえたりするためで、せまくて暗い場所を好むのと似た理由です。
高い場所に猫の生活空間をつくると、安心できるだけでなく、上下に移動範囲を広げることができるので、運動不足の解消につながります。
高所を確保する方法としては、キャットタワーの設置が一般的です。
さまざまな高さがあるので部屋の状況や猫の成長に合わせて選ぶといいでしょう。小部屋が設置されているものを選べば、高さ、せまさ、暗さを兼ね備えた空間を用意してあげることができます。
このように、猫は必ずしも居住スペースに広さを必要としません。むしろせまさが重要です。
一人暮らし用の部屋など決して広くない場所でも環境のつくり方次第で、ストレスを与えることなく猫を飼うことは十分可能です。
これも外敵から身を守ったり、獲物を捕らえたりするためで、せまくて暗い場所を好むのと似た理由です。
高い場所に猫の生活空間をつくると、安心できるだけでなく、上下に移動範囲を広げることができるので、運動不足の解消につながります。
高所を確保する方法としては、キャットタワーの設置が一般的です。
さまざまな高さがあるので部屋の状況や猫の成長に合わせて選ぶといいでしょう。小部屋が設置されているものを選べば、高さ、せまさ、暗さを兼ね備えた空間を用意してあげることができます。
このように、猫は必ずしも居住スペースに広さを必要としません。むしろせまさが重要です。
一人暮らし用の部屋など決して広くない場所でも環境のつくり方次第で、ストレスを与えることなく猫を飼うことは十分可能です。
猫のための部屋づくり ②脱走・誤飲対策

猫を室内で飼ううえでもっともも気を付けなければならないトラブルが、脱走と誤飲です。しっかりと対策を行ってあげましょう。
脱走対策
猫は基本的に自分のテリトリー内で過ごすことを好みますが、外へ出る機会をうかがう好奇心の強いタイプもいて、脱走してしまうケースも少なくありません。
外の怖さを知らない猫ほど危ない目に遭う確率も高くなるので、注意が必要です。
脱走経路として考えられるのは、玄関ドア、窓、ベランダの3カ所です。それぞれに対策を行いましょう。
玄関ドアからの脱走防止には、玄関の手前に小型の簡易扉を設置するのが有効です。
突っ張り棒を使用するタイプもあるので、賃貸住宅でも設置は可能です。
簡易的にフェンスを置くだけでも効果はあります。猫はジャンプ力があるので、なるべく高さがあるものを選ぶといいでしょう。
窓は数が多いので、特に気を配りたいポイントです。
空気や風を取り込むときには網戸は開けないようにしましょう。自分で網戸をあけることができる猫もいるので油断はできません。
網戸ストッパーなどを設置し、開かないようにすると効果的です。
また、爪が鋭い状態だと網戸を破る可能性もあります。定期的な爪切りをするとともに、できるなら網戸を頑丈なタイプに替えるといいでしょう。
ベランダは直接外に接しているため、基本的に猫が出入りできるような状態にすべきではありません。
しかし、生活の都合上難しい場合には、必ず対策をしてください。具体的にはネットなどを使い、ベランダを覆ってしまうなどの方法がおすすめです。
外の怖さを知らない猫ほど危ない目に遭う確率も高くなるので、注意が必要です。
脱走経路として考えられるのは、玄関ドア、窓、ベランダの3カ所です。それぞれに対策を行いましょう。
玄関ドアからの脱走防止には、玄関の手前に小型の簡易扉を設置するのが有効です。
突っ張り棒を使用するタイプもあるので、賃貸住宅でも設置は可能です。
簡易的にフェンスを置くだけでも効果はあります。猫はジャンプ力があるので、なるべく高さがあるものを選ぶといいでしょう。
窓は数が多いので、特に気を配りたいポイントです。
空気や風を取り込むときには網戸は開けないようにしましょう。自分で網戸をあけることができる猫もいるので油断はできません。
網戸ストッパーなどを設置し、開かないようにすると効果的です。
また、爪が鋭い状態だと網戸を破る可能性もあります。定期的な爪切りをするとともに、できるなら網戸を頑丈なタイプに替えるといいでしょう。
ベランダは直接外に接しているため、基本的に猫が出入りできるような状態にすべきではありません。
しかし、生活の都合上難しい場合には、必ず対策をしてください。具体的にはネットなどを使い、ベランダを覆ってしまうなどの方法がおすすめです。
誤飲防止
猫は好奇心旺盛な生き物なので、目につくあらゆる物に手を出して遊びます。そのまま好きにさせると、危険なものを誤って飲み込んでしまうこともあるため、注意しましょう。
まず、クリップ、輪ゴム、アクセサリー類などの飲み込みやすい小さなものや、タバコや薬など食べてしまうと危険なものは、猫の手の届くところには置かないようにしましょう。また、観葉植物のなかには猫が口にすると中毒を起こすものがあります。飾っている場合は猫に安全なものか調べ、危険な種類の場合は猫が届かないところへ移動するなど、対策をしてください。
猫はかなり高いところまでジャンプして移動できるので、危ないものはどこかにしまっておくのが無難です。
食べ物も戸棚などにしっかり閉まっておきましょう。袋に入っていても破って取り出すことがあります。
掃除と整理整頓を習慣化し、誤飲すると危険なものが放置されてない状態にしておくことが、一番の対策です。
まず、クリップ、輪ゴム、アクセサリー類などの飲み込みやすい小さなものや、タバコや薬など食べてしまうと危険なものは、猫の手の届くところには置かないようにしましょう。また、観葉植物のなかには猫が口にすると中毒を起こすものがあります。飾っている場合は猫に安全なものか調べ、危険な種類の場合は猫が届かないところへ移動するなど、対策をしてください。
猫はかなり高いところまでジャンプして移動できるので、危ないものはどこかにしまっておくのが無難です。
食べ物も戸棚などにしっかり閉まっておきましょう。袋に入っていても破って取り出すことがあります。
掃除と整理整頓を習慣化し、誤飲すると危険なものが放置されてない状態にしておくことが、一番の対策です。
猫のための部屋づくり ③爪とぎの設置

猫にとって爪をとぐことは生活の一部です。
獲物を刈るためのお手入れ、マーキングの手段として、自己アピールや単なる気分転換のためなど、さまざまな理由で爪をとぎます。
放っておくと壁や家具など部屋中が傷だらけになってしまうため、早いうちからの対策が必要です。
生後1カ月くらいから爪とぎを始めるので、早めに爪とぎ器を設置し、その場所で行うようしつけましょう。
爪とぎには紙タイプ、板タイプ、麻縄タイプなどさまざまな種類があり、猫によって好むものが異なります。
柱に巻きつけるものや直接床におくもの、壁にとりつけるものなど、種類豊富なので、猫の好みと部屋の状況に合うものを選びましょう。
ただ、残念ながら、爪とぎ器を用意してもほかの場所で爪をといでしまうことも多いです。
壁には保護シートを貼る、爪をといで欲しくない場所にはスプレーなどで猫の嫌うにおいをつけておくなどの、次善策を打っておくことをおすすめします。
保護シートを使用するときは、猫の全長(身長)と同じくらいの高さまで貼る必要があります。猫は思いっきり背を伸ばして爪をとぐためです。
スプレーで対策を行う場合、猫に有害な成分が含まれていない、専用商品を使用するようにしましょう。
獲物を刈るためのお手入れ、マーキングの手段として、自己アピールや単なる気分転換のためなど、さまざまな理由で爪をとぎます。
放っておくと壁や家具など部屋中が傷だらけになってしまうため、早いうちからの対策が必要です。
生後1カ月くらいから爪とぎを始めるので、早めに爪とぎ器を設置し、その場所で行うようしつけましょう。
爪とぎには紙タイプ、板タイプ、麻縄タイプなどさまざまな種類があり、猫によって好むものが異なります。
柱に巻きつけるものや直接床におくもの、壁にとりつけるものなど、種類豊富なので、猫の好みと部屋の状況に合うものを選びましょう。
ただ、残念ながら、爪とぎ器を用意してもほかの場所で爪をといでしまうことも多いです。
壁には保護シートを貼る、爪をといで欲しくない場所にはスプレーなどで猫の嫌うにおいをつけておくなどの、次善策を打っておくことをおすすめします。
保護シートを使用するときは、猫の全長(身長)と同じくらいの高さまで貼る必要があります。猫は思いっきり背を伸ばして爪をとぐためです。
スプレーで対策を行う場合、猫に有害な成分が含まれていない、専用商品を使用するようにしましょう。
猫のための部屋づくり ④快適な温度設定

猫は暑さに強く寒さに弱い生き物です。祖先であるリビアヤマネコが砂漠で暮らしていたためです。
室内ならエアコンによる温度調整が簡単にできるので、猫にとって心地いい温度に調整してあげましょう。
夏場の快適な温度は28℃くらいです。冷えすぎを防ぐため、エアコンの温度は下げすぎないようにしてください。
冬場はなるべく暖かくしてあげるようにしましょう。エアコンの設定温度は最低でも18℃以上にしてください。
温度調節が難しい子猫やシニア猫の場合は、年間を通して28℃前後に保ち、寒暖差をできるだけ抑えるようにするといいです。
なお、エアコン以外にも、クールマットや湯たんぽ、ペットヒーターなどが温度の調節手段としてあげられます。
ストーブを使用するときは、熱風が直接当たらないタイプを使用しましょう。猫が近づきすぎてやけどする可能性があります。
可能ならば石油ストーブよりはファンヒーターを使用した方が安全です。
また、猫は自分にとって快適な場所を探すのが得意なので、なるべく自由に移動できるような環境づくりも有効です。
室内ならエアコンによる温度調整が簡単にできるので、猫にとって心地いい温度に調整してあげましょう。
夏場の快適な温度は28℃くらいです。冷えすぎを防ぐため、エアコンの温度は下げすぎないようにしてください。
冬場はなるべく暖かくしてあげるようにしましょう。エアコンの設定温度は最低でも18℃以上にしてください。
温度調節が難しい子猫やシニア猫の場合は、年間を通して28℃前後に保ち、寒暖差をできるだけ抑えるようにするといいです。
なお、エアコン以外にも、クールマットや湯たんぽ、ペットヒーターなどが温度の調節手段としてあげられます。
ストーブを使用するときは、熱風が直接当たらないタイプを使用しましょう。猫が近づきすぎてやけどする可能性があります。
可能ならば石油ストーブよりはファンヒーターを使用した方が安全です。
また、猫は自分にとって快適な場所を探すのが得意なので、なるべく自由に移動できるような環境づくりも有効です。
まとめ

猫は室内で飼育するのが基本。猫が喜ぶ部屋づくりをするためには、キャットタワーや爪とぎを設置してストレスをためないようにしたり、猫にとって心地よい室温設定をしたり工夫するとよいでしょう。
愛猫とのよりよい暮らしのために、快適な環境づくりをしてみてください。
愛猫とのよりよい暮らしのために、快適な環境づくりをしてみてください。
関連する記事


【実例も紹介】狭くても大丈夫! 猫がゴキゲンになる部屋づくり5つのポイント
猫が落ち着く部屋とはどんな空間でしょうか。一人暮らしの狭い部屋でもマンションでも、レイアウト次第で猫が快適に暮らせる部屋作りができます。
執筆者プロフィール
『みんなのペットライフ』編集部スタッフが、わんちゃん・ねこちゃんの飼い方、しつけのアドバイスなど、毎日のペットライフに役立つ知識や情報をお届けします。
猫のブリーダーについて

魅力たっぷりの猫をあなたも迎えてみませんか?
おすすめは、ブリーダーとお客様を直接つなぐマッチングサイトです。国内最大のブリーダーズサイト「みんなの子猫ブリーダー」なら、優良ブリーダーから健康的な子猫を迎えることができます。
いつでもどこでも自分のペースで探せるのがインターネットの魅力。「みんなの子猫ブリーダー」では写真や動画、地域などさまざまな条件で理想の猫を探せるほか、多数の成約者の口コミが揃っています。気になる方はぜひ参考にしてみてくださいね。
※みんなの子猫ブリーダーに移動します