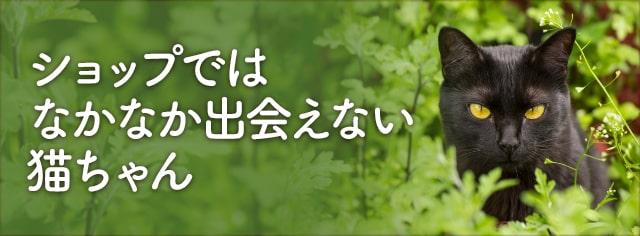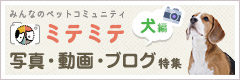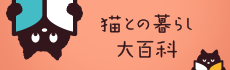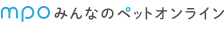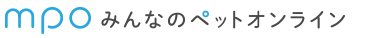なぜ猫は爪とぎをするの? 意味は?
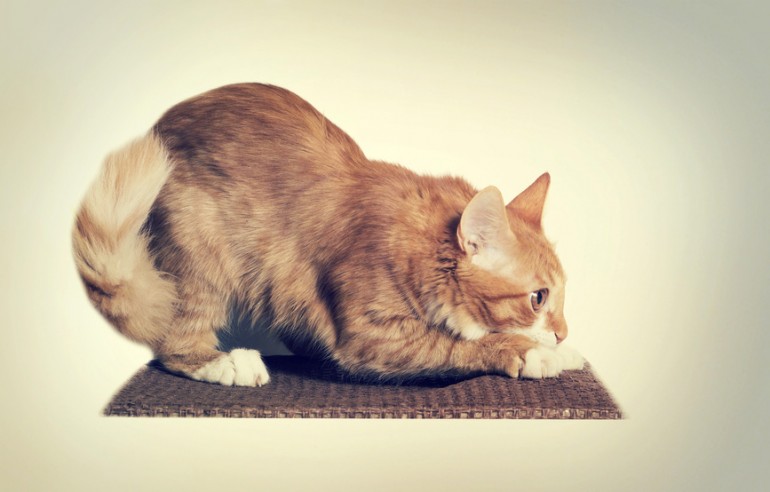
爪のケア
ストレス解消や気分転換
もし頻繁に爪とぎをするなら、ストレスを溜め込んでいる可能性もあります。注意して見てあげましょう。
マーキング
自己アピール
もしあなたが帰宅した直後の爪とぎであれば、「帰ってきたぁ! 遊んで!」と喜びを爆発させてるのでしょう。
食事や飲み水を欲しがっていることもあるので、様子を観察し、要求に応えてあげてください。
猫の爪とぎ器の種類について

そのときに役に立つのが「爪とぎ器」。
ペットショップや通販などでさまざまな種類の爪とぎ器が販売されており、手軽に購入することができます。
それぞれの特徴を踏まえて、飼い猫が気に入りそうなものを選んであげましょう。
紙、段ボールタイプ
スーパーやホームセンターなどで気軽に購入できるだけでなく、値段が手頃なのも、飼い主には嬉しいポイント。
しかし、強度が弱く、重量も軽いので、力の強い猫はすぐにボロボロにしてしまったり、場所を移動させてしまったりすることもあります。
交換頻度が高く、散らかったクズをこまめに掃除したり、位置をもとに戻したりしなくてはならない点はデメリットといえるでしょう。

木目調のプリントでインテリアになじむデザインの段ボール製爪とぎ。段ボール製で、爪とぎだけでなくベッドとして利用する猫も多いようです。
麻縄、綿縄タイプ
キャットタワーや柱など、好みの場所に巻きつけるなどして自作することもできます。ゴミが出にくいので、掃除の心配もほとんどいりません。
ただし、麻には独特の臭いがあるため、猫によっては見向きもしない可能性もあります。

長い麻ひもタイプの爪とぎです。伸びあがって爪とぎをするのが好きな猫にぴったりです。80cmと長いので、大型の猫にも向いています。
布タイプ
爪をといでもカスが出にくく、設置は床に敷くだけでOK。おしゃれなデザインのものが多いので、インテリアにこだわる方にもおすすめです。
麻のような臭いもなく長持ちしますが、価格は紙や麻のものと比べると若干割高。加えて、布の爪とぎ器と感触が似ているため、カーペットで爪とぎをするようになってしまうケースがあります。

椅子やテーブルの脚などに巻き付けて使える布製の爪とぎです。家具を爪とぎから守るだけでなく、新たに爪とぎを設置しなくてもいいので、スペースの節約にもなります。
木材タイプ
多少の削りクズは出るものの、猫は本来木で爪をとぐため、猫の習性に合った素材であるともいえます。また、猫が家のどこかで爪とぎをするようになってしまった場合、その箇所を覆うように設置することも可能です。
ただし、価格はほかの爪とぎ器と比べて高価なものになっています。
また、無骨な見た目のものが多いので、人によっては好き嫌いが分かれるかもしれません。

天然杉を使用した国産の木製爪とぎ。家の角に設置するタイプで、ぼろぼろになったら裏返せばまた使用できるため、長く使うことができます。
猫に爪とぎをしつける方法

無理にやめさせたり、過剰に怒ったりせず、根気よく時間をかけてしつけに取り組むようにしましょう。
仮に指定した場所以外で爪をといでしまったときは怒らず、様子を観察してください。猫の好みを知れる、絶好の機会です。
柔らかい場所なら紙やダンボール素材、椅子や家具など固いものなら麻縄や木製の爪とぎを用意してあげるといいかもしれません。
もし壁やソファ、カーペットなど指定以外の場所で爪とぎを始めたら「爪とぎをしてもいい場所」に優しく導いてあげてください。間違っても大声を出したり、叩いたりするのはNGです。
「爪とぎをしてもいい場所」の理想は、テレビの横など常に人間の目線が向かう場所です。
猫にとって爪とぎは自分の存在をアピールする行為。誰かに爪とぎを見られることで、自己顕示欲を高められるのです。
自分から指定の場所で爪とぎしたときは、頭をなでて褒めてあげましょう。これを根気よく繰り返すことで、徐々に爪をといでもいい場所を覚えさせることができます。
猫の爪とぎ対策

まずはさまざまな素材の爪とぎ器を複数用意し、それらを適切な場所に設置してください。
やはり猫によって好む素材は異なるので、お気に入りの爪とぎ器を特定することが先決です。
また、爪とぎをされたくない場所にはしっかり対策を講じましょう。
壁紙のような傷みやすいものは、保護シートやプラスチック段ボールで覆い、保護することをおすすめします。ペット用のものが数千円で販売しており、必要なサイズへのカットや貼り替えも簡単に行うことができます。
100円均一ショップで購入できるプラスチック性のシートや段ボールでも代用することもできます。
合皮や布など、爪が引っかかりやすい素材のソファも爪とぎの標的となりやすいです。爪とぎのしつけが完了するまでは、傷んでもよいソファカバーを被せておきましょう。
物理的に保護する以外には、爪とぎ防止スプレーを利用するという方法もあります。
これは猫が嫌がる柑橘類やココナッツの匂いがするスプレーで、猫が近寄るのを防ぐことができます。ただし、匂いに慣れてしまう場合もあるので、確実性はシートや段ボールに劣ります。
そして、さまざまな対策のなかで最も効果的な方法は、定期的に爪を切ること。
これは壁などを守るだけでなく、人間がひっかかれてケガをしてしまうリスクも抑えることができます。猫の健康状態を管理するという意味でも、爪が伸びすぎていないか定期的にチェックしてみてください。
まとめ

爪とぎが猫の本能である以上、しっかりとしつけと対策を行い、共生できるように折り合いをつけるしかありません。人と猫がお互いストレスなく暮らすため、ぜひこの記事を参考にしてみてください。

自分で爪とぎをする猫ですが、爪切りは猫の安全のために必要です。爪を切る必要性や頻度、タイミングや、暴れる場合の対処方法についてまとめました。
猫のブリーダーについて

魅力たっぷりの猫をあなたも迎えてみませんか?
おすすめは、ブリーダーとお客様を直接つなぐマッチングサイトです。国内最大のブリーダーズサイト「みんなの子猫ブリーダー」なら、優良ブリーダーから健康的な子猫を迎えることができます。
いつでもどこでも自分のペースで探せるのがインターネットの魅力。「みんなの子猫ブリーダー」では写真や動画、地域などさまざまな条件で理想の猫を探せるほか、多数の成約者の口コミが揃っています。気になる方はぜひ参考にしてみてくださいね。