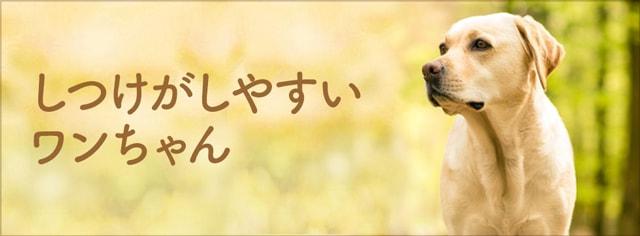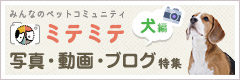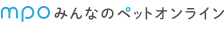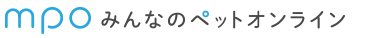性別の組み合わせで相性が異なる?

「オス×メス」の場合
ケンカや争いごとが起きにくい性別の組み合わせといわれています。大人びて気が強いメスと、行動が分かりやすく甘えん坊なオスという性格的な傾向を持つことから、精神面での関係性がはっきりしやすい分、多頭飼いをする上で相性の問題が起こりづらい組み合わせとされています。
オス×メスの組み合わせの場合、気をつけたいポイントは発情期です。飼い主さんが子犬を望まないのであれば、生後6カ月前後に迎える性成熟期を前に、去勢・避妊手術は必ず行うようにしましょう。可能であればオス・メスの両方に不妊処置を行いたいところです。
オス×メスの組み合わせの場合、気をつけたいポイントは発情期です。飼い主さんが子犬を望まないのであれば、生後6カ月前後に迎える性成熟期を前に、去勢・避妊手術は必ず行うようにしましょう。可能であればオス・メスの両方に不妊処置を行いたいところです。
「オス×オス」の場合
オス同士の組み合わせは、多頭飼いが最も難しい組み合わせです。特に年齢の近いオスは縄張り意識が非常に高く、群れのなかで「リーダーになりたい、優位に立ちたい」という習性が競争心をあおります。
無用な争いを避けるためにも、群れのリーダーは「飼い主さん」であるということを犬に認識させる必要があります。新たに迎えた犬へとルールを教えられるよう、先住犬にしっかりとしつけを行っておきましょう。
無用な争いを避けるためにも、群れのリーダーは「飼い主さん」であるということを犬に認識させる必要があります。新たに迎えた犬へとルールを教えられるよう、先住犬にしっかりとしつけを行っておきましょう。
「メス×メス」の場合
メスは他者へあまり干渉しない性格を持つ傾向があるということから、オス同士より飼いやすい組み合わせといわれています。
ただし、オスほどではないものの、メスにも順番づけの争いはあります。メス同士を多頭飼いする場合でも、飼い主さんがリーダーシップをとってしつけをすることに変わりはありません。
ただし、オスほどではないものの、メスにも順番づけの争いはあります。メス同士を多頭飼いする場合でも、飼い主さんがリーダーシップをとってしつけをすることに変わりはありません。
異なる体のサイズを持つ犬を多頭飼いするポイント

多頭飼いは「小型犬×小型犬」など、サイズの近い犬同士が基本的に望ましいとされています。では、体のサイズが大きく違う犬を多頭飼いする場合には、どんな点に気をつければよいのでしょうか?
思わぬケガに注意
小型犬×大型犬を多頭飼いする場合、普段の遊びやじゃれあいのなかで、いくつか気をつけたいポイントがあります。
・2頭で走り回っているうちに、小型犬が大型犬に押しつぶされた
・大型犬は遊んで噛んだつもりでも、小型犬にとっては大きなダメージになる
・動き回るものを捕食する習性から、小型犬が噛まれた
犬に悪気はなくとも、体格差から小型犬がアクシデントでケガを負う可能性は決してゼロではありません。もしケンカをはじめてしまった場合、力そのものに大きな差があるので危険です。
【小型犬×大型犬を上手に多頭飼いするには?】
「小型犬×大型犬」という組み合わせで多頭飼いを行う場合、先住犬が小型犬であれば比較的うまくいきやすいといわれています。
室内飼いのなかで、しっかりとしつけられている先住犬がいる場合、力や強さだけでは順番づけをせず、賢く優れた犬のほうが上位となるので体の大きさはあまり影響しません。
となれば、サイズ的に室内飼いしやすい小型犬はしつけをしやすく、先住犬として適しているという訳です。
・2頭で走り回っているうちに、小型犬が大型犬に押しつぶされた
・大型犬は遊んで噛んだつもりでも、小型犬にとっては大きなダメージになる
・動き回るものを捕食する習性から、小型犬が噛まれた
犬に悪気はなくとも、体格差から小型犬がアクシデントでケガを負う可能性は決してゼロではありません。もしケンカをはじめてしまった場合、力そのものに大きな差があるので危険です。
【小型犬×大型犬を上手に多頭飼いするには?】
「小型犬×大型犬」という組み合わせで多頭飼いを行う場合、先住犬が小型犬であれば比較的うまくいきやすいといわれています。
室内飼いのなかで、しっかりとしつけられている先住犬がいる場合、力や強さだけでは順番づけをせず、賢く優れた犬のほうが上位となるので体の大きさはあまり影響しません。
となれば、サイズ的に室内飼いしやすい小型犬はしつけをしやすく、先住犬として適しているという訳です。
運動量の差に配慮を
小型犬と大型犬は歩幅が大きく異なるため、一緒に散歩へ出かけることは難しいとされています。もし一緒に出掛けるときには、小型犬はキャリーバッグや専用のベビーカーに乗せて移動するなど、工夫をしましょう。
一日に必要とされる運動量も小型犬と大型犬では大きく違うので、それぞれ別々のタイミングで散歩へと出かけるほうがよいかもしれませんね。
一日に必要とされる運動量も小型犬と大型犬では大きく違うので、それぞれ別々のタイミングで散歩へと出かけるほうがよいかもしれませんね。
犬種の組み合わせは多頭飼いに影響する?

同じ犬種同士の組み合わせで多頭飼いを行う場合、特徴が近くなるため相性がよくなりやすいといわれています。一方、異なる犬種の組み合わせで多頭飼いする場合には、相性の良し悪しはさほど影響しないといわれています。
犬種ごとで考えると、群れをあまり好まない特徴を持つテリア種など多頭飼いにあまり向かないとされる犬種はあります。ですが、テリア種すべての個体が当てはまるわけではなく、順応性の高い個体もいるので、しつけをしっかりと行えば問題なく多頭飼いができる場合もあります。
犬種ごとで考えると、群れをあまり好まない特徴を持つテリア種など多頭飼いにあまり向かないとされる犬種はあります。ですが、テリア種すべての個体が当てはまるわけではなく、順応性の高い個体もいるので、しつけをしっかりと行えば問題なく多頭飼いができる場合もあります。
犬と猫を一緒に飼う場合

■子犬と子猫を同時に迎える場合
同じまたは近い月齢の子犬と子猫だと、多頭飼いがしやすいとされています。特に、生後2~3カ月齢ごろに迎える「社会化期」は、他者の存在を認識し社会性を身につける時期です。
社会化期には精神面が大きく成長し、他者との関係を築いていきます。よき遊び相手として、なかよく育っていくでしょう。
■先住犬(成犬)がおり、子猫を迎える場合
犬は群れで生活していたため、他者に対して寛容です。犬が先住している多頭飼いの場合、関係性の構築は犬社会のルールで行われます。それは、「群れ」として上下関係を重視したコミュニケーション方法です。
新しく迎えた子猫も群れの一員として扱われ、先住犬はリーダーシップを持って子猫に接していきます。単独行動を好むとされる猫も、子猫の時代から群れのルールを教えられるため多頭飼いに順応していきやすくなります。
同じまたは近い月齢の子犬と子猫だと、多頭飼いがしやすいとされています。特に、生後2~3カ月齢ごろに迎える「社会化期」は、他者の存在を認識し社会性を身につける時期です。
社会化期には精神面が大きく成長し、他者との関係を築いていきます。よき遊び相手として、なかよく育っていくでしょう。
■先住犬(成犬)がおり、子猫を迎える場合
犬は群れで生活していたため、他者に対して寛容です。犬が先住している多頭飼いの場合、関係性の構築は犬社会のルールで行われます。それは、「群れ」として上下関係を重視したコミュニケーション方法です。
新しく迎えた子猫も群れの一員として扱われ、先住犬はリーダーシップを持って子猫に接していきます。単独行動を好むとされる猫も、子猫の時代から群れのルールを教えられるため多頭飼いに順応していきやすくなります。
先住犬が攻撃性の強い性格の場合
ひとつ気をつけておきたいことは、先住犬の攻撃性が強い場合です。
まだ幼い子猫は好奇心いっぱいで、あちらこちらを動き回ります。縄張りのなかで猫があまりに自由に動き回ると、犬が気になってつい手を出してしまうこともあります。そうならないために、先住犬の攻撃性をセーブするためにしっかりとしつけを行いましょう。
そして、最初から犬と猫の距離を近づけ過ぎないことがポイントです。接する時間を徐々に増やしながら、様子を見て互いの距離を縮めていくようにしましょう。
■先住猫(成猫)がおり、子犬を迎える場合
集団行動を好む犬とは異なり、猫は単独行動を好む習性があります。すでに成長している猫は自らのペースで行動するので、後から来た子犬の存在でペースを乱されるとストレスを感じやすくなり、関係性がうまく構築できません。体調にも悪影響が出ます。
猫の生活ペースが乱されないよう、猫が独りでいれるような場所づくりを行うなど環境的な配慮をとりましょう。
そして、子犬には群れで生きる習性を利用したしつけを行います。子犬にとって、猫が群れの上位(リーダーは飼い主さん)だと覚えさせていきましょう。しつけを繰り返すうちに少しずつ猫との適切な距離をつかみ、関係性をつくっていけるようになります。
まだ幼い子猫は好奇心いっぱいで、あちらこちらを動き回ります。縄張りのなかで猫があまりに自由に動き回ると、犬が気になってつい手を出してしまうこともあります。そうならないために、先住犬の攻撃性をセーブするためにしっかりとしつけを行いましょう。
そして、最初から犬と猫の距離を近づけ過ぎないことがポイントです。接する時間を徐々に増やしながら、様子を見て互いの距離を縮めていくようにしましょう。
■先住猫(成猫)がおり、子犬を迎える場合
集団行動を好む犬とは異なり、猫は単独行動を好む習性があります。すでに成長している猫は自らのペースで行動するので、後から来た子犬の存在でペースを乱されるとストレスを感じやすくなり、関係性がうまく構築できません。体調にも悪影響が出ます。
猫の生活ペースが乱されないよう、猫が独りでいれるような場所づくりを行うなど環境的な配慮をとりましょう。
そして、子犬には群れで生きる習性を利用したしつけを行います。子犬にとって、猫が群れの上位(リーダーは飼い主さん)だと覚えさせていきましょう。しつけを繰り返すうちに少しずつ猫との適切な距離をつかみ、関係性をつくっていけるようになります。
まとめ

今回は身体的な特徴から、犬の多頭飼いについて考えてきました。犬の性格や個性を育むのは飼い主さんですから、やはりしつけ上手であることが、上手な多頭飼いの実現につながる最大のコツなのかもしれませんね。次回は、実際に多頭飼いを行う際のポイントについてご紹介します。
前回・次回の記事はこちら
前回・次回の記事はこちら
関連する記事


犬の多頭飼い(2)-先住犬の性格と精神面から考える
前回の犬の多頭飼い特集では、多頭飼いのメリットとデメリットを中心にご紹介しました。今回は、先住犬の性格や精神面に注目して多頭飼いのポイントを考えていきます。先住犬の性格を考慮した多頭飼いを行い、新...

犬の多頭飼い(4)-多頭飼いをはじめるタイミング、ケージやトイレなどの環境
犬の多頭飼いの特集も今回で4回目。多頭飼いのメリットやデメリット、性格・精神面など先住犬との関係性、そして前回は性別や体のサイズによる組み合わせなど多頭飼いを検討する際のポイントについてご紹介して参...
執筆者プロフィール
『みんなのペットライフ』編集部スタッフが、わんちゃん・ねこちゃんの飼い方、しつけのアドバイスなど、毎日のペットライフに役立つ知識や情報をお届けします。
犬のブリーダーについて

魅力たっぷりの犬をあなたも迎えてみませんか?
おすすめは、ブリーダーとお客様を直接つなぐマッチングサイトです。国内最大のブリーダーズサイト「みんなのブリーダー」なら、優良ブリーダーから健康的な子犬を迎えることができます。
いつでもどこでも自分のペースで探せるのがインターネットの魅力。「みんなのブリーダー」では写真や動画、地域などさまざまな条件で理想の犬を探せるほか、多数の成約者の口コミが揃っています。気になる方はぜひ参考にしてみてくださいね。
※みんなのブリーダーに移動します