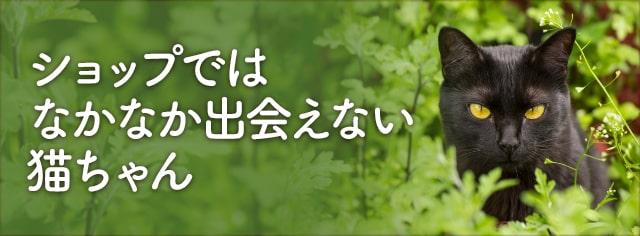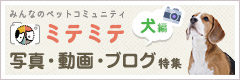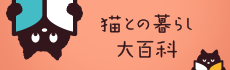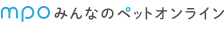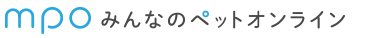猫の一生は短い? 長い? 人間の年齢に換算すると……

猫の平均寿命は最新の調査では14.3歳※1と発表されています。一見、短命にも感じられますが、人間の年齢に換算すると76~78歳程度になります。日本人の平均寿命が男性で81.09歳、女性で87.26歳(厚生労働省 平成29年簡易生命表より)であることを考えるとそれほど違和感はありませんよね。
ちなみに、世界の長寿記録はアメリカの「クレームパフ」という猫。ギネスブックに38年と3日間生きたと記録されていますが、人間に換算すると168歳まで生きたことになります。これほど長寿ではなくとも飼い猫には長生きしたもらいたいもの。猫の年齢を人間に置き換えると、年齢による猫の身体の変化のイメージが掴みやすくなり、健康管理にも役立ちます。
※1 アニコム家庭どうぶつ白書2021
ちなみに、世界の長寿記録はアメリカの「クレームパフ」という猫。ギネスブックに38年と3日間生きたと記録されていますが、人間に換算すると168歳まで生きたことになります。これほど長寿ではなくとも飼い猫には長生きしたもらいたいもの。猫の年齢を人間に置き換えると、年齢による猫の身体の変化のイメージが掴みやすくなり、健康管理にも役立ちます。
※1 アニコム家庭どうぶつ白書2021
人間なら何歳になる? ライフステージ別の飼い方

幼年期/生まれてから~生後6ヵ月未満(人間の0~7歳)
まさに伸び盛りの時期。社会性も身に付けよう
生まれてから半年はハイスピードで成長する時期。この時期は人間の0~7歳にあたります。小学校入学くらいまでと考えるとイメージしやすいでしょうか。特に生後3~9週は「社会化期」とも言われており、親猫や兄弟猫と過ごすことでコミュニケーションを学びます。
猫の生まれた直後は目や耳が閉じていますが、生後約10日程度で開き、ものが見えるように、音が聞こえるようになります。また、歩き始めるのもこの頃です。1カ月前後で乳歯が生え揃い、それにともない離乳食に移行していきます。まだ消化器官が未発達のため、フードはあらかじめ消化吸収を考慮してつくられている幼猫用のフードを与えましょう。消化しやすいよう少量を1日数回に分けて与えます。
3カ月を過ぎる頃になると永久歯が生えてくるので「噛み癖」など困った癖がつかないよう、生後3カ月頃までにしつけができるとベストです。
生まれてから半年はハイスピードで成長する時期。この時期は人間の0~7歳にあたります。小学校入学くらいまでと考えるとイメージしやすいでしょうか。特に生後3~9週は「社会化期」とも言われており、親猫や兄弟猫と過ごすことでコミュニケーションを学びます。
猫の生まれた直後は目や耳が閉じていますが、生後約10日程度で開き、ものが見えるように、音が聞こえるようになります。また、歩き始めるのもこの頃です。1カ月前後で乳歯が生え揃い、それにともない離乳食に移行していきます。まだ消化器官が未発達のため、フードはあらかじめ消化吸収を考慮してつくられている幼猫用のフードを与えましょう。消化しやすいよう少量を1日数回に分けて与えます。
3カ月を過ぎる頃になると永久歯が生えてくるので「噛み癖」など困った癖がつかないよう、生後3カ月頃までにしつけができるとベストです。

最初のワクチン接種は生後2カ月頃が目安
ちなみに、生後2カ月くらいまでは母親の初乳からもらう抗体のおかげでウイルス感染を予防できますが、2~4カ月経つとこの抗体がなくなると言われています。そのため、ワクチンは生後2~4カ月の間に数回摂取するのが理想とされています。まず、初回のワクチン摂取の目安は生後2カ月頃と覚えておきましょう。
ちなみに、生後2カ月くらいまでは母親の初乳からもらう抗体のおかげでウイルス感染を予防できますが、2~4カ月経つとこの抗体がなくなると言われています。そのため、ワクチンは生後2~4カ月の間に数回摂取するのが理想とされています。まず、初回のワクチン摂取の目安は生後2カ月頃と覚えておきましょう。
青少年期/6~12カ月未満(人間の8~16歳)
発情期を迎える時期
この時期は人間で言えば、どんどん体が大きくなり、大人になる準備をしようとする頃。猫も生後6か月を過ぎ、7~8カ月頃になると永久歯に完全に生え変わり、成猫のように噛むことができるようになります。
また、この頃から発情の兆候が見られるようになります。一般的に避妊、去勢手術をするなら発情期を迎える前が理想ですが、体が小さすぎると手術の麻酔に耐えられない可能性もあります。手術のタイミングはあらかじめ獣医師によく相談しておきましょう。
強すぎる猫の繁殖力
ちなみに猫は非常に繁殖力が強く、妊娠から出産までの期間は2ヵ月ほどで、年に3~4回も出産することもあります。放っておくとあっという間にどんどん子猫が増えていき手に負えなくなることもあります。繁殖目的がないのであれば避妊、去勢手術をおすすめします。
この時期は人間で言えば、どんどん体が大きくなり、大人になる準備をしようとする頃。猫も生後6か月を過ぎ、7~8カ月頃になると永久歯に完全に生え変わり、成猫のように噛むことができるようになります。
また、この頃から発情の兆候が見られるようになります。一般的に避妊、去勢手術をするなら発情期を迎える前が理想ですが、体が小さすぎると手術の麻酔に耐えられない可能性もあります。手術のタイミングはあらかじめ獣医師によく相談しておきましょう。
強すぎる猫の繁殖力
ちなみに猫は非常に繁殖力が強く、妊娠から出産までの期間は2ヵ月ほどで、年に3~4回も出産することもあります。放っておくとあっという間にどんどん子猫が増えていき手に負えなくなることもあります。繁殖目的がないのであれば避妊、去勢手術をおすすめします。
成年期/1~6歳(人間の17~40歳)
成熟した体が完成する
1歳を過ぎるともう立派な大人。骨格や体型は生後1年ほどで完成し、いわゆる成猫となります。毛並みもツヤも良くなり、人間でたとえるなら健康な若者の時期です。食事はこの時期に成猫用に切り替えましょう。
3歳以上の猫のほとんどが歯周病になる?
1歳を過ぎるともう立派な大人。骨格や体型は生後1年ほどで完成し、いわゆる成猫となります。毛並みもツヤも良くなり、人間でたとえるなら健康な若者の時期です。食事はこの時期に成猫用に切り替えましょう。
3歳以上の猫のほとんどが歯周病になる?

歯周病にも注意しましょう。実は3歳以上の猫の8割は歯周病と言われています。猫は歯石化するまでの時間が約1週間と短く、歯みがきを怠ると歯周病予備軍になってしまいます。歯周病にならないためにも、できるだけ若いうちから歯磨きには慣れさせておきたいものです。
中高年期/7~10歳(人間の44~56歳)
次第に衰えが見られる時期
猫の場合、一般的に7歳を過ぎるとシニア期に入ったと捉えられます。だんだんと運動能力に衰えが見られるようになり、寝ている時間も増えていきます。また、消化機能も衰えてくるため、食事は段階的にシニア用のフードに切り替える時期でもあります。個体差はあるものの、一度に多くの量を食べられなくなってくるため、猫の体調に合わせて食事回数を増やして(例:1日3~4回程度)、少量づつ与えるようにしましょう。
メタボに注意! 健康管理は今まで以上に
特に、健康管理には今まで以上に気を配りたいものです。たとえばこれまで1年に1度だった定期健康診断を半年に一度のペースに増やすなど、病気の予防や早期発見に努めましょう。歯周病はもちろんのこと、肥満にも要注意。肥満は糖尿病や心臓病を引き起こす原因にもなるので、食事量やカロリーの管理を徹底しましょう。
猫の場合、一般的に7歳を過ぎるとシニア期に入ったと捉えられます。だんだんと運動能力に衰えが見られるようになり、寝ている時間も増えていきます。また、消化機能も衰えてくるため、食事は段階的にシニア用のフードに切り替える時期でもあります。個体差はあるものの、一度に多くの量を食べられなくなってくるため、猫の体調に合わせて食事回数を増やして(例:1日3~4回程度)、少量づつ与えるようにしましょう。
メタボに注意! 健康管理は今まで以上に
特に、健康管理には今まで以上に気を配りたいものです。たとえばこれまで1年に1度だった定期健康診断を半年に一度のペースに増やすなど、病気の予防や早期発見に努めましょう。歯周病はもちろんのこと、肥満にも要注意。肥満は糖尿病や心臓病を引き起こす原因にもなるので、食事量やカロリーの管理を徹底しましょう。
老年期/11~16歳(人間の60~83歳)

一日のほとんどを寝て過ごす
体力が衰えているので、動くことが負担になってきます。そのため、一日のほとんどを寝て過ごすように。毛づくろいの回数も減ってくるため毛艶も失われはじめます。食事量も減ってくるため、少量でも栄養やカロリー補給できるシニア向けのキャットフードを選ぶと良いでしょう。
高齢ならではの病気に注意
人間と同じですが、高齢にともない病気にかかりやすくなります。一般的に高齢猫がかかりやすいと言われている病気には慢性腎不全や糖尿病、がんなどがあります。猫種によってかかりやすい病気も異なるので、あらかじめ調べておいて予防に努めるようにしましょう。歯周病もまた、全身の老化を加速させるとも言われているので注意が必要です。口が臭い、歯がぐらつく、出血しているなど気になる症状は見逃さず、病院に連れていきましょう。
体力が衰えているので、動くことが負担になってきます。そのため、一日のほとんどを寝て過ごすように。毛づくろいの回数も減ってくるため毛艶も失われはじめます。食事量も減ってくるため、少量でも栄養やカロリー補給できるシニア向けのキャットフードを選ぶと良いでしょう。
高齢ならではの病気に注意
人間と同じですが、高齢にともない病気にかかりやすくなります。一般的に高齢猫がかかりやすいと言われている病気には慢性腎不全や糖尿病、がんなどがあります。猫種によってかかりやすい病気も異なるので、あらかじめ調べておいて予防に努めるようにしましょう。歯周病もまた、全身の老化を加速させるとも言われているので注意が必要です。口が臭い、歯がぐらつく、出血しているなど気になる症状は見逃さず、病院に連れていきましょう。
超高齢期/17歳以上(人間の84歳以上)
寝たきりになることも
猫が17歳は、人間の84歳ぐらいに相当します。米寿(数え年で88歳)に近いと考えると、まさに「ご長寿」ですよね。この年齢になると、食も細くなり動きが目に見えて衰えてきます。足が弱くなったり、病気などで動けなくなり寝たきりのような状態になることも。寝床に床ずれ防止マットを敷くなど、猫が穏やかに安心して生活ができるような環境作りが必要です。
猫が17歳は、人間の84歳ぐらいに相当します。米寿(数え年で88歳)に近いと考えると、まさに「ご長寿」ですよね。この年齢になると、食も細くなり動きが目に見えて衰えてきます。足が弱くなったり、病気などで動けなくなり寝たきりのような状態になることも。寝床に床ずれ防止マットを敷くなど、猫が穏やかに安心して生活ができるような環境作りが必要です。
まとめ

換算年齢は目安ですが、人間に置き換えると体の衰えなどのイメージもつきやすいのではないでしょうか? 平均寿命は15年程度でも、飼育環境や健康に気を配れば、より健やかに長生きできる可能性はじゅうぶんにあります。普段から健康管理などに気を配り、長生きできるよう努めるのも飼い主の役目ですね。
関連する記事


子猫のコミュ力を磨く遊び方って? おすすめのおもちゃも紹介します
子猫期の遊びは、社会性を養う大切なもの。これはコミュニケーション能力を磨くことでもあります。子猫の飼い主さんは、親猫の代わりに教えてあげなければいけません。ここでは、子猫のコミュニケーション能力を...
執筆者プロフィール
『みんなのペットライフ』編集部スタッフが、わんちゃん・ねこちゃんの飼い方、しつけのアドバイスなど、毎日のペットライフに役立つ知識や情報をお届けします。
猫のブリーダーについて

魅力たっぷりの猫をあなたも迎えてみませんか?
おすすめは、ブリーダーとお客様を直接つなぐマッチングサイトです。国内最大のブリーダーズサイト「みんなの子猫ブリーダー」なら、優良ブリーダーから健康的な子猫を迎えることができます。
いつでもどこでも自分のペースで探せるのがインターネットの魅力。「みんなの子猫ブリーダー」では写真や動画、地域などさまざまな条件で理想の猫を探せるほか、多数の成約者の口コミが揃っています。気になる方はぜひ参考にしてみてくださいね。
※みんなの子猫ブリーダーに移動します