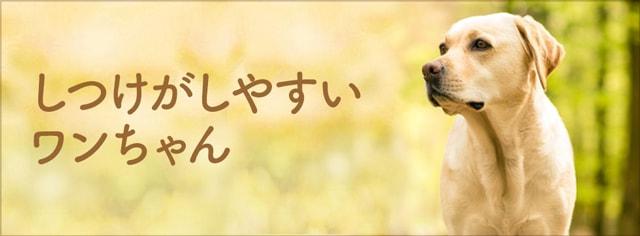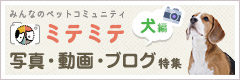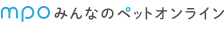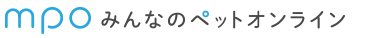1.犬の入手方法は「ブリーダー」や「里親」がおすすめ

犬種が決まっているならブリーダーもおすすめ
メリット
・流通コスト(中間マージンなど)が上乗せされていない分、良質な子犬をペットショップより安価で購入できることも
・犬としてのルールを学ぶべき時期(社会化期)を母犬や兄弟犬と一緒に過ごしているので、迎えた後もしつけやすい
・ブリーダーに飼い方やしつけ方のアドバイスを仰げる
・犬が生まれ育った環境を知ることができるので、健康的な子犬と出会うことができる
(正しい飼養管理の知識があるブリーダーの犬舎で育った犬なら健康的に飼われていると推察できる)
・遺伝病検査をしているブリーダーの下で生まれた子犬なら、遺伝病にかかるリスクが低い
(将来、子犬が遺伝病を発症するリスクを回避するため、計画的な繁殖を行っているということ)
デメリット
・遠方のブリーダーから迎える場合、交通費がかかる(高額になることもある)
・人気ブリーダーの場合、すぐに子犬を購入できないことがある

しかし、それは犬種標準(スタンダード)に近い犬を目指して、質の向上に真摯に取り組んでいるからこそ。優れたブリーダーのもとで生まれた子犬は心身ともに素晴らしい資質を持っています。メリットも多いブリーダーからの購入、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。ブリーダーにとっても、心血を注いで育てた子犬を渡すのですから、飼い主の顔が見えることは何よりの安心材料になるはずです。
小さな命を救うために。里親になる方法
ただし、犬によっては病気や怪我を抱えていたり、老化による衰えで手助けが必要なケースもあります。「終生飼養」は飼い主の義務。里親になる前に、自分がどんな犬を引き取ろうとしていて、どんなお世話が必要なのか、最後までお世話ができるのかじっくり考えることが必要です。
2.飼い主が知るべき2大法律「狂犬病予防法」と「動物愛護管理法」

「狂犬病予防法」で定められた義務を知ろう
飼い主には次の3点が義務付けられています。
・犬の登録…犬を飼い始めたら、住んでいる自治体に届出をすること
・予防接種…年1回、飼い犬に狂犬病の予防接種を受けさせること
・鑑札と注射済票の装着…犬の鑑札と注射済票を飼い犬に付けること

狂犬病予防のために飼い主がすべきことを確認しましょう。
狂犬病とは、犬はもちろんのこと、人を含むすべての哺乳類が感染し、発病するとほぼ100%の確率で死に至る恐ろしい病気です。動物の検疫業務を行う農林水産省によれば、「日本、アイスランド、オーストラリア、ニュージーランド、フィジー諸島、ハワイ、グアム」の7地域しか「狂犬病が発生していない地域」と認められていません。
狂犬病に関する詳しい説明はこちら
農林水産大臣が指定している狂犬病の清浄国・地域が確認できます。
「動物愛護管理法」はペットに関わるすべての人に向けた法律

この法律には、
・動物に合った飼養環境を整える
・終生世話をする
・人の社会に合った飼い方をする
・病気に対する知識を持つ
など、守らなければならないことが定められています。
環境省のホームページでは、飼い主に向けて役立つ情報がまとめられています。これを読むと飼い主として守るべきポイントや、動物取扱業者を選ぶときのポイントなどがわかりますよ。
飼い主の方に役立つ情報がまとめられています。
3.生涯必要経費は120万円? 犬の飼育に必要な費用を予習しよう

アニコムが発表している「家庭どうぶつ白書2021」によれば、犬の1年間の飼育にかかる費用は、338,561円ですが、具体的にどのような費用がかかるのでしょうか。飼育にかかる費用の項目をご紹介します。考えるときの参考にしてみてくださいね。
初期費用の目安(飼い始めの1年目にかかる費用)
・畜犬登録費:3,000円
・狂犬病予防接種代:3,500円
・混合ワクチン代(2回分):15,000円前後
・飼養管理に必要なグッズ:30,000円前後
合計 151,500円~
毎年必要な費用の目安(年間費用)
・混合ワクチン代:10,000円前後
・寄生虫やフィラリア予防薬代:15,000円前後
・食費:50,000円前後(フードのグレードによる)
・トイレグッズなど消耗品費:20,000円前後
・トリミングやケア代:40,000~150,000円前後(犬種による)
・その他、オモチャ代や衣服代など
年額合計 300,000円前後
ケースバイケースで必要な費用(1回当たりの費用)
・避妊手術(メス):40,000~80,000円前後
・その他、病気の治療費
動物病院の医療費の考え方

・診察料:1,000円前後
・薬代:体重に比例して必要な量が増えるので、大型犬の方が高くなる
・検査費用:血液検査、糞便検査、目の検査などさまざま。1検査あたり2,000円前後
・点滴や輸液:4,000円前後
・レントゲン検査や超音波検査:5,000円前後
・手術費=術前検査費+技術費+麻酔代+薬代+入院費+リハビリ代+術後検査費
病気や手術内容によっては、1,000,000円を超えるケースもあります
高額な医療費には、保険もしくは積み立てで対応
獣医師の診療料金は、独占禁止法により、獣医師団体(獣医師会等)が基準料金を決めたり、獣医師同士が協定して料金を設定したりすることが禁じられています。つまり、現行法のもとでは獣医師は各自が料金を設定し、競争できる体制を維持しなければならないことになっております。したがって動物病院によって料金に格差があるのはやむを得ない状況と言えます。

・こまめに健康診断を受ける
・予防のための薬・ワクチンを活用する
このほかにも、日頃からの適切な健康管理で犬を病気から守ることができます。
犬・猫の診療料金実態調査の結果がまとめられています。近所の動物病院の費用と合わせて参考にしてみてください。
4.みんなに愛される犬に育てる「しつけ」はマンツーマンで!
人の社会のルールを教えるのは飼い主の役目
犬を飼う場合、飼い主がリーダーになります。「従わせるなんてかわいそう!」と思う方もいるかもしれません。しかし、犬はもともと群れで生活していた動物であり、リーダーが群れを統率していました。リーダーシップを発揮できる強い犬に従うことで、安心して過ごせていたのです。愛犬が安心して生活するためには、飼い主が犬を守り、人との社会ルールを教え、安心できる居場所と満足できる食事を与える必要があります。

たとえば「スワレ」の指示で座るようにしつける場合、「スワレ」と声をかけ、犬が座る動作を取るよう手を添え、座れば褒める。このように「コマンド(指示の言葉)と動作」を関連づけて覚えさせます。なでてもらう、おやつをもらうなど犬にとってうれしい「ご褒美」を使えば、より早くスムーズに覚えてくれます。
どんなしつけが必要なの?
・トイレトレーニング
・「ハウス」という指示でケージやクレートに入らせる
・移動用キャリーの中で静かに待たせる
・無駄吠え対策
・留守番
・飛び付きを止めさせる
・噛み癖を直す
上記はあくまでも一例です。状況に応じ必要なしつけやトレーニングは変わるので多少ハードに感じるかもしれません。しかし、犬がきちんと指示に従えれば、人の社会の中でも周囲に迷惑をかけない「利口な犬」として受け入れられます。
犬のしつけは根気が必要です。このようなトレーニングを誰が、どのようにして毎日取り組むのか。犬を飼う前にしっかり考えておきたいものです。
5.犬が寝たきりになったら、きちんと介護できますか?

さらに10歳を過ぎると体力や免疫力が低下し、病気にかかりやすくなります。寝たきりになってしまう犬もいるでしょう。体が不自由になれば介護が必要になります。また、徘徊・遠吠えが止まらないなど認知症になるケースもあります。
このように、犬の老後のケアが必要になる可能性もあると頭に入れておきましょう。特に体重が20~30kgを超える大型犬の場合、介護は体力勝負になります。犬はかわいくて安らぎを与えてくれる存在ですが、ともに暮らすためにはそれ相応のお世話が必要なのです。
幸せなドッグライフを送るために

犬も長寿の時代となった今、15年前後という長いスパンで生活を考えなければなりません。犬、そして家族の成長など、家庭の中や家計が大きく変化する分岐点はたくさんありますよね。
「犬を飼いたい!」そう思ったら、まずは家族みんなでこれから先、犬と暮らす15年間の未来予想図を描いてみましょう。うれしいことや悲しいこと、困難なことなどさまざまな場面に出会うと思います。飼い主として責任をもって犬を育てられるか、よく向き合ってみてくださいね。

犬の飼い主にとっては、毎年4~6月の予防接種でおなじみの狂犬病。飼い犬に予防注射を受けさせるのは飼い主の義務ですが、予防注射の接種率は年々減少傾向にあるとのこと。狂犬病とはどんな病気で、ワクチンを接...
犬のブリーダーについて

魅力たっぷりの犬をあなたも迎えてみませんか?
おすすめは、ブリーダーとお客様を直接つなぐマッチングサイトです。国内最大のブリーダーズサイト「みんなのブリーダー」なら、優良ブリーダーから健康的な子犬を迎えることができます。
いつでもどこでも自分のペースで探せるのがインターネットの魅力。「みんなのブリーダー」では写真や動画、地域などさまざまな条件で理想の犬を探せるほか、多数の成約者の口コミが揃っています。気になる方はぜひ参考にしてみてくださいね。