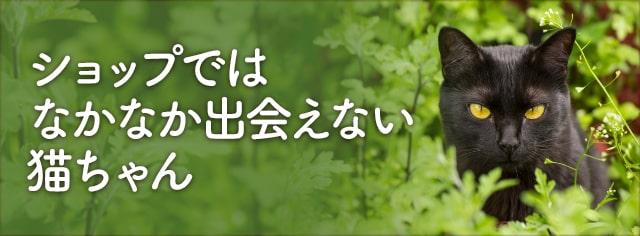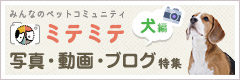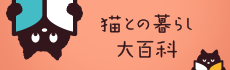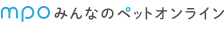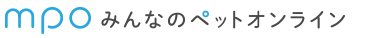猫の下痢の原因

病気以外では、食事が原因で下痢になることもあります。
ごはんを多く食べたり、脂肪分の多いものを食べたりすると、胃腸に負荷がかかって下痢になります。
急にフードを替えたときや、普段と違ったものを食べさせた場合、特に子猫は体が対応しきれずに便が緩くなることが多いです。
ちなみに、食事の変化で下痢が起こったときは、注意が必要です。
単におなかがびっくりしただけならよいのですが、食事性のアレルギーがあった場合、食事に含まれる何らかの成分が消化できないケースがあるからです。
2、3日経っても下痢が治らなかったり、嘔吐や皮膚のかゆみなどが出たりするならば、その食事はすぐ中止しましょう。
また、乳製品を食べさせた場合も、乳糖を分解(消化)できないことから、おなかを壊す可能性が高いです。
そのほか、ストレスが原因で下痢が起こることもあります。
例えば、年末年始やお盆に見知らぬ人がたくさん家を訪れた、季節の変わり目で急に寒くなったり暑くなったりしたなど、急な環境の変化があると、自律神経のバランスが崩れて下痢になることがあります。
そして、飲み薬、特に抗生物質の副作用でも下痢をします。
飲み薬は胃や腸で吸収されるため、その過程でおなかの細菌叢のバランスを壊してしまう場合があるのです。
薬を飲み始めて数日で急におなかが緩くなるようなら、すぐに中止して処方された動物病院に相談しましょう。

猫と一緒に生活をしていると、うっかり落とした食べ物を食べられてしまった……なんてこともあるかと思います。人間が平気で食べているものでも、猫の体に良くないものがあり、おなかを壊わすなどのトラブルが起こ...

神経質な一面を持つ猫、ストレスから病気になることもあります。猫がストレスを感じているときのサイン(症状)や原因、解消法について説明します。
猫の下痢から考えられる病気

寄生虫感染
ほかの病気の感染がなければ、ほとんどの猫は元気で食欲もありますが、緩い便が長く続きます。
寄生虫感染は、糞便検査で診断がつきやすく、飲み薬や滴下薬で治療ができます。
特に子猫を迎えいれた際は、便が緩いと感じなくても、一度動物病院での糞便検査をおすすめします。
ウイルス感染
ウイルスが消化管に影響をおよぼし、下痢と嘔吐が主な症状になりますが、元気の低下や食欲不振が起こったり、発熱したりすることもあります。
治療は点滴での水分の補給や、抗生物質で細菌感染のコントロールを行いますが、子猫はもともとの体力が乏しいため、治療のかいなく命を落としてしまう場合も少なくありません。
この病気の特徴は、混合ワクチンによる予防が有効だということです。
子猫を新しく迎え入れた場合は、なるべく早く混合ワクチンを打つことをおすすめします。このとき、先住猫がいるならば、先住猫にも忘れずにワクチンを打ってください。
もうひとつ、猫白血病ウイルスと猫免疫不全ウイルス、および猫コロナウイルスによる感染でも下痢が起こります。
これらのウイルスの感染初期は無症状なことが多いですが、感染している猫の免疫力が下がったときに症状が現れます。
下痢の症状は慢性で、嘔吐や体重の減少も認められます。残念ながら根本的な治療法はなく、発症すると命に関わることが多いです。
感染はウイルスを持っている猫との接触で起こりますので、愛猫はなるべく外に出さないで飼うことをおすすめします。

猫を飼い始めたとき、最初に気になるのは健康状態と今後の予防についてだと思います。皆さんは、猫を感染症から守るためにワクチンがあるのをご存じですか。今回は、ワクチンの接種時期や種類、予防できる病気な...
その他
猫の危険な下痢を見分けるポイント

まずは愛猫の状態を見てください。元気や食欲はありますか? 嘔吐などほかの症状はないですか? おなかを気にしたり頻繁に伸びの姿勢をしたりするなど、おなかが痛いそぶりを見せたりしませんか?
1回緩い便が出ても、元気で便の異常以外に変わった様子が認められず、次にした便が正常な硬さなら、自宅で様子を見てもいいでしょう。
便以外の異常が見られたり、一回便が硬くなっても、また緩くなったりと症状を繰り返す場合は、病院を受診してください。
また、血が混じったり大量の粘液が混じったりするときも、早めに受診しましょう。
下痢でしぶりが出ているときは、肛門付近の細かい血管が切れて血が混じりやすくなります。
もともと腸は便を排出するために粘液を分泌しているので、少量の粘液は便に付着するものです。
しかし、明らかに認められる血液や多量の粘液は、腫瘍や炎症の兆候であることもありますので、見逃さないようにしましょう。
獣医師は、いくつかの手掛かりから、下痢の原因を探ります。
いつから症状があるのか、便のかたさや排便の回数、1回にした便の量の増減、しぶりや腹痛がないかなど、飼い主に質問することが多いです。余裕があれば、愛猫のこれらの状態を把握してから、動物病院を受診するとよいですね。

猫のうんちに血がついている?そんな時は要注意。軟便・下痢かどうか、鮮血か、タール状の黒色便か、嘔吐はあるかなどを確認し、医師に伝えましょう。
家庭でできる猫の下痢の対処法

便の状態が悪くなってすぐのときは、食事は1回の量を、いつも食べさせる1/4~1/2くらいにしてください。可能ならば食事の回数自体を増やして、1回に食べる量を、何回かに分けて食べさせてあげましょう。
また、ドライフードを主に食べさせている場合は、消化をよくするためにふやかして食べさせるのも、おなかによいです。
ただし、ふやかしたドライフードは、猫によって好みが分かれ、嫌がってまったく食べない猫もいます。愛猫の嗜好に合わせてトライしてください。
その際、熱湯でふやかすとフードの栄養素が壊れやすいため、ぬるま湯でふやかすようにするとよいでしょう。
人間でも体調を崩すとおなかを壊しやすい人がいる一方で、熱が出やすい人もいますよね。そういった個体差があるように、猫にも体質による個体差があります。
下痢を繰り返すものの大きな病気を認めない場合は、体質が原因のこともあるので、普段から消化のよいフードに変更してください。
各メーカーで消化器によいと記載がある食事を選ぶといいでしょう。その際、できれば獣医師に相談して、病院で購入できる処方食を選べば、より高い効果が期待されます。
まとめ

まずはワクチンや駆虫など、基本的な予防ができているかもう一度見直してください。そして、下痢になってしまったときは、食事に気を付けて、動物病院への早めの受診を心がけてください。

愛猫のうんち、普段から観察していますか? 実は猫は便秘になりやすい動物なんです。「たかが便秘」と軽く考えがちですが、病気が隠れていることもあるほか、放っておくと慢性化して他の病気を引き起こすことも。...
猫のブリーダーについて

魅力たっぷりの猫をあなたも迎えてみませんか?
おすすめは、ブリーダーとお客様を直接つなぐマッチングサイトです。国内最大のブリーダーズサイト「みんなの子猫ブリーダー」なら、優良ブリーダーから健康的な子猫を迎えることができます。
いつでもどこでも自分のペースで探せるのがインターネットの魅力。「みんなの子猫ブリーダー」では写真や動画、地域などさまざまな条件で理想の猫を探せるほか、多数の成約者の口コミが揃っています。気になる方はぜひ参考にしてみてくださいね。