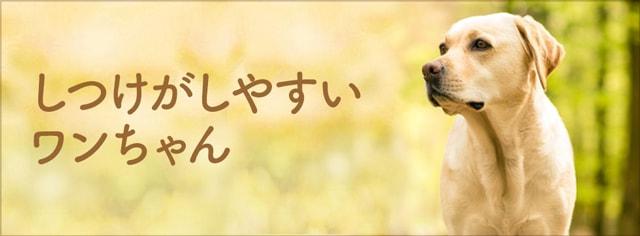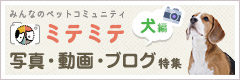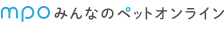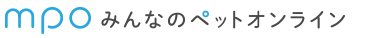犬がうれしょんする理由

まずは、犬はどのような理由でうれしょんをするのか、理由を見ていきましょう。
粗相との違い
うれしょんとは、犬が興奮した場合などにおしっこを漏らしてしまう行為のことです。決められた場所以外でおしっこをすることから粗相ともとらえられがちですが、単なる「失敗」とは違います。
ほとんどの犬は、おしっこをする場合は周辺のにおいを嗅ぐなどの準備行動をとります。しかし、うれしょんの場合には、なんの素振りもなくそのままおしっこを漏らしてしまうのです。
ほとんどの犬は、おしっこをする場合は周辺のにおいを嗅ぐなどの準備行動をとります。しかし、うれしょんの場合には、なんの素振りもなくそのままおしっこを漏らしてしまうのです。
漏らす量は犬によって違う
うれしょんで漏らす尿は通常の排尿に比べると少ないことが一般的ですが、犬によって量には違いがあります。
散歩中の排尿が習慣になっている場合に膀胱におしっこがたまりがちで、うれしょんの量も多い傾向にあります。
散歩中の排尿が習慣になっている場合に膀胱におしっこがたまりがちで、うれしょんの量も多い傾向にあります。
楽しい、うれしいなど喜びが爆発
うれしょんはその名の通り、楽しさや嬉しさ、喜びのあまり興奮しすぎることが原因となり、おっしっこを漏らすことです。
帰宅時にうれしょんする犬が多いですが、これは留守番で寂しい思いをしたあとに大好きな飼い主が帰ってきたため、感情が高ぶっておしっこを漏らしてしまうのです。
帰宅時にうれしょんする犬が多いですが、これは留守番で寂しい思いをしたあとに大好きな飼い主が帰ってきたため、感情が高ぶっておしっこを漏らしてしまうのです。
おしっこを漏らすと反応してくれる
愛犬がうれしょんをしたとき、慌てて名前を呼んだり、構ったりすることはありませんか?
このときの飼い主のリアクションを、「喜んでいる」と犬が勘違いしていまうケースもあります。このような勘違いが原因となり、もっと喜んでもらいたくてうれしょんを繰り返すことも少なくないようです。
このときの飼い主のリアクションを、「喜んでいる」と犬が勘違いしていまうケースもあります。このような勘違いが原因となり、もっと喜んでもらいたくてうれしょんを繰り返すことも少なくないようです。
服従心の現れ
犬にはおしっこを漏らすことで服従心をアピールする習性があります。その場合、うれしょんの原因は興奮ではなく、本能によるものと言えるでしょう。
うれしょんしやすい犬の特徴

うれしょんしやすい犬の特徴を見ていきましょう。どの特徴に当てはまるかを見極めることで、その後の対策もしやすくなります。ぜひチェックしてみてください。
子犬
まだ感情を抑えることができない子犬は、ちょっとしたことで興奮してしまうので、成犬と比べてうれしょんをしやすい傾向にあります。
それに加えて、尿を溜めておくための筋肉が成長過程であることから、思うように排泄をコントロールできないのも原因のひとつです。
また、月齢を重ねていても、小型犬の場合にはうれしょんの確率が高くなるといわれています。これは、体の小さい小型犬は服従する対象が多いため、本能的にうれしょんをしやすいのではないかと考えられています。
それに加えて、尿を溜めておくための筋肉が成長過程であることから、思うように排泄をコントロールできないのも原因のひとつです。
また、月齢を重ねていても、小型犬の場合にはうれしょんの確率が高くなるといわれています。これは、体の小さい小型犬は服従する対象が多いため、本能的にうれしょんをしやすいのではないかと考えられています。
興奮しやすい性格
うれしょんの原因のひとつは「興奮」ですので、興奮しやすく、落ち着きのない性格の犬はうれしょんしやすい傾向にあります。
臆病
気が弱くて臆病な性格の犬や、精神面が不安定な犬も、うれしょんの確率は高くなります。
特に、今までは問題なかったのに最近急にうれしょんが増えたというケースでは、大きなストレスを抱えていることがあります。
生活環境の変化なども大きく影響するので、愛犬の心理状態には十分気を配ましょう。
特に、今までは問題なかったのに最近急にうれしょんが増えたというケースでは、大きなストレスを抱えていることがあります。
生活環境の変化なども大きく影響するので、愛犬の心理状態には十分気を配ましょう。
飼い主に依存している
飼い主への依存心が高い犬も、比較的うれしょんしやすいです。
この場合も服従心が大きく関係していて、自身をアピールするための本能的な行動だといえるでしょう。
この場合も服従心が大きく関係していて、自身をアピールするための本能的な行動だといえるでしょう。
犬のうれしょん、やめさせるには

次に、犬にうれしょんをやめさせる方法について見ていきましょう。
年齢とともにしなくなることが多い
うれしょんは年齢とともに自然に治ることが多いので、子犬の場合は焦らずに長い目で見てあげてください。
個体差があるため、何歳になったら必ず治ると言い切ることはできませんが、1歳くらいを目安にしてみるとよいでしょう。
個体差があるため、何歳になったら必ず治ると言い切ることはできませんが、1歳くらいを目安にしてみるとよいでしょう。
しつけのポイント
子犬期を過ぎ、成犬になってもうれしょんが治らない場合には、しつけで改善を目指しましょう。しつけにあたってのポイントを紹介します。
①興奮させないようにする
うれしょんの防止には、なるべく興奮させないことがとても大切です。愛犬が興奮していると感じた場合には、近寄ってきてもスルーするなど、完全に落ち着くまで構わないで無視しておきましょう。
かわいい愛犬を無視のは辛いかもしれませんが、愛犬の心を落ち着かせるためには一番効果があります。これを繰り返すことで、「興奮しているときには構ってもらえない」と学習し、徐々に感情のコントロールも上手になっていくでしょう。
②叱らない
うれしょんをやめさせるためには、叱らないことも大切です。
犬も飼い主を困らせたいわけではありません。うれしょんは興奮したり、服従心をアピールしたりするための結果です。
悪気がない相手に対して一方的に叱ってしまうと、犬は驚くだけでなく、とても悲しい気持ちになります。
また、場合によっては「叱られる=反応してくれる」と勘違いしてすることもあります。
うれしょんによって飼い主の気を引くことができると、間違って覚えかねません。気を付けましょう。
③帰宅時の注意点
帰宅時には、愛犬が興奮するような声掛けをしないことも大切なポイントです。
飼い主からしても愛犬に会えるのはうれしいことですので、つい高く大きめな声で名前を呼びたくなりますが、そこはぐっと我慢。愛犬の興奮をあおらないようにしましょう。
また、愛犬は飼い主の姿を見ただけでもうれしくて興奮します。その場合は興奮が収まってから声をかけてあげるようにしてください。
そして、うれしょんをしてしまった場合でも、慌てたり大きな声を出したりせず、愛犬を無視しつつ淡々と後始末をしてください。これを繰り返すことで、うれしょんをしてもいいことはないと認識させられます。
④興奮状態でもコマンドを聞くように練習
興奮状態が少し落ち着いてきたら、「お座り」「待て」などのコマンドを出してみましょう。コマンドを出されることで冷静な気持ちを取り戻す場があります。できたらたっぷりと褒めてあげてください。
①興奮させないようにする
うれしょんの防止には、なるべく興奮させないことがとても大切です。愛犬が興奮していると感じた場合には、近寄ってきてもスルーするなど、完全に落ち着くまで構わないで無視しておきましょう。
かわいい愛犬を無視のは辛いかもしれませんが、愛犬の心を落ち着かせるためには一番効果があります。これを繰り返すことで、「興奮しているときには構ってもらえない」と学習し、徐々に感情のコントロールも上手になっていくでしょう。
②叱らない
うれしょんをやめさせるためには、叱らないことも大切です。
犬も飼い主を困らせたいわけではありません。うれしょんは興奮したり、服従心をアピールしたりするための結果です。
悪気がない相手に対して一方的に叱ってしまうと、犬は驚くだけでなく、とても悲しい気持ちになります。
また、場合によっては「叱られる=反応してくれる」と勘違いしてすることもあります。
うれしょんによって飼い主の気を引くことができると、間違って覚えかねません。気を付けましょう。
③帰宅時の注意点
帰宅時には、愛犬が興奮するような声掛けをしないことも大切なポイントです。
飼い主からしても愛犬に会えるのはうれしいことですので、つい高く大きめな声で名前を呼びたくなりますが、そこはぐっと我慢。愛犬の興奮をあおらないようにしましょう。
また、愛犬は飼い主の姿を見ただけでもうれしくて興奮します。その場合は興奮が収まってから声をかけてあげるようにしてください。
そして、うれしょんをしてしまった場合でも、慌てたり大きな声を出したりせず、愛犬を無視しつつ淡々と後始末をしてください。これを繰り返すことで、うれしょんをしてもいいことはないと認識させられます。
④興奮状態でもコマンドを聞くように練習
興奮状態が少し落ち着いてきたら、「お座り」「待て」などのコマンドを出してみましょう。コマンドを出されることで冷静な気持ちを取り戻す場があります。できたらたっぷりと褒めてあげてください。
犬のうれしょんは病気?
最後に、うれしょんは病気の可能性があるかどうか、見ていきましょう。
うれしょん自体は病気ではない
ここまでお伝えしてきたように、うれしょん自体は、興奮や本能、成長過程が原因で起こることが多く、基本的には病気ではありません。
ただし、しつけをしても治らない場合や、あまり興奮していないのにうれしょんする場合には、膀胱炎などの病気の疑いが潜んでいることも覚えておきましょう。愛犬がうれしょんする状況をよく観察し、もしかしたらと不安がある場合には、獣医師に相談してみてください。
ただし、しつけをしても治らない場合や、あまり興奮していないのにうれしょんする場合には、膀胱炎などの病気の疑いが潜んでいることも覚えておきましょう。愛犬がうれしょんする状況をよく観察し、もしかしたらと不安がある場合には、獣医師に相談してみてください。
落ち着くのを待ちましょう
うれしょんを避けたい状況には、オムツやマナーベルトなどを活用するのもよいでしょう。
根本的な改善策ではありませんので日常的に使うのはおすすめしませんが、掃除の負担軽減にも役立つはずです。グッズなどを上手に活用しながら、うれしょん防止のしつけを行っていきましょう。
根本的な改善策ではありませんので日常的に使うのはおすすめしませんが、掃除の負担軽減にも役立つはずです。グッズなどを上手に活用しながら、うれしょん防止のしつけを行っていきましょう。
まとめ

今回は、犬がうれしょんをする理由や、やめさせ方についてお伝えしました。
飼い主のことが大好きだからこそ、愛犬はうれしょんしてしまいます。それをやめさせるためには愛犬を興奮させないこと、落ち着くまで無視することなどがポイントです。
飼い主にとっては辛い試練になりますが、正しく身に付けられるまでの我慢ですので、愛犬と一緒に頑張ってみてください!
飼い主のことが大好きだからこそ、愛犬はうれしょんしてしまいます。それをやめさせるためには愛犬を興奮させないこと、落ち着くまで無視することなどがポイントです。
飼い主にとっては辛い試練になりますが、正しく身に付けられるまでの我慢ですので、愛犬と一緒に頑張ってみてください!
執筆者プロフィール
『みんなのペットライフ』編集部スタッフが、わんちゃん・ねこちゃんの飼い方、しつけのアドバイスなど、毎日のペットライフに役立つ知識や情報をお届けします。
犬のブリーダーについて

魅力たっぷりの犬をあなたも迎えてみませんか?
おすすめは、ブリーダーとお客様を直接つなぐマッチングサイトです。国内最大のブリーダーズサイト「みんなのブリーダー」なら、優良ブリーダーから健康的な子犬を迎えることができます。
いつでもどこでも自分のペースで探せるのがインターネットの魅力。「みんなのブリーダー」では写真や動画、地域などさまざまな条件で理想の犬を探せるほか、多数の成約者の口コミが揃っています。気になる方はぜひ参考にしてみてくださいね。
※みんなのブリーダーに移動します