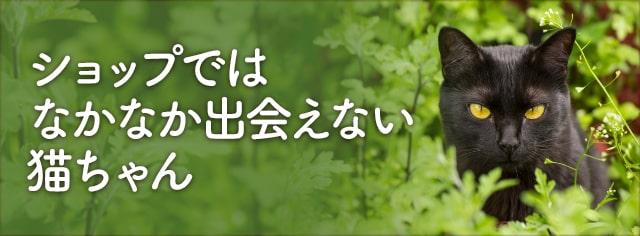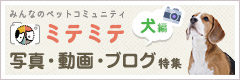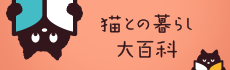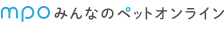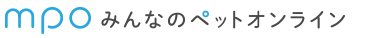猫が水を飲まない理由

猫は本来、あまり水を飲まない動物です。
現在の猫は、砂漠に住んでいたリビアヤマネコの子孫だと言われています。砂漠は水が乏しいため、リビアヤマネコは少ない水分でも生きていける体に進化しました。猫のおしっこは濃い色で少ないですが、それは体内でぎゅっと濃縮しているから。水分を過剰に排出しないための工夫です。
しかし、水をあまり必要としないことの弊害もあります。体が水分を必要とする状態でも、猫はのどの渇きを感知するのが苦手なのです。
健康なときでもあまり水分をとらないのは危険ですが、特に老齢などで腎臓の働きが弱まった猫や、肥満で保水力の足りない猫だと、脱水症状を起こしやすくなります。体全体のうち、子猫のときには80~90%、成猫で60~70%が水分。下痢などで体内の10%以上の水分が失われると死に至る可能性もあります。
水分が少ない状態が続くと、腎臓病や尿路系の疾患にもかかりやすくなるようです。
猫が水を飲みたがらないからといって、体内に必要な水分が足りているわけではないのです。
現在の猫は、砂漠に住んでいたリビアヤマネコの子孫だと言われています。砂漠は水が乏しいため、リビアヤマネコは少ない水分でも生きていける体に進化しました。猫のおしっこは濃い色で少ないですが、それは体内でぎゅっと濃縮しているから。水分を過剰に排出しないための工夫です。
しかし、水をあまり必要としないことの弊害もあります。体が水分を必要とする状態でも、猫はのどの渇きを感知するのが苦手なのです。
健康なときでもあまり水分をとらないのは危険ですが、特に老齢などで腎臓の働きが弱まった猫や、肥満で保水力の足りない猫だと、脱水症状を起こしやすくなります。体全体のうち、子猫のときには80~90%、成猫で60~70%が水分。下痢などで体内の10%以上の水分が失われると死に至る可能性もあります。
水分が少ない状態が続くと、腎臓病や尿路系の疾患にもかかりやすくなるようです。
猫が水を飲みたがらないからといって、体内に必要な水分が足りているわけではないのです。
猫が脱水を起こしているときの症状

猫が脱水を起こしているとき、どんな症状があるのでしょうか。
まずは皮膚をつまんでみてください。通常時なら手を離せばすぐもとに戻りますが、脱水を起こしているとつままれた形のまますぐには戻りません。肉球の色や鼻の色がいつもと違って見えるときも要注意。毛づやが悪くなったり、歯ぐきが乾燥したりといった症状もあります。
下痢や嘔吐しているときや暑い場所に長時間いたときなど、このような症状が見られたら脱水を起こしている可能性があります。
まずは皮膚をつまんでみてください。通常時なら手を離せばすぐもとに戻りますが、脱水を起こしているとつままれた形のまますぐには戻りません。肉球の色や鼻の色がいつもと違って見えるときも要注意。毛づやが悪くなったり、歯ぐきが乾燥したりといった症状もあります。
下痢や嘔吐しているときや暑い場所に長時間いたときなど、このような症状が見られたら脱水を起こしている可能性があります。
猫が一日に必要とする水分量

尿を含めて猫が一日に失う水分は、体重1kgあたり60~70mlといわれています。
ただし、この量をすべて飲み水のみで補わなくてはならないわけではなく、食べものに含まれる水分でも摂取できます。気温や湿度によっても必要な量は変わりますね。筋肉には水分をたくわえられるため、猫の筋肉量によっても変動します。
「必要な量は自分で取るはず」と思うかもしれませんが、本当にそうでしょうか。放っておいて大丈夫なら、肥満や中毒、誤飲などを心配する必要はありません。
猫はのどの渇きに鈍感なので、飼い主が水を飲ませる工夫をすることが必要です。
ただし、この量をすべて飲み水のみで補わなくてはならないわけではなく、食べものに含まれる水分でも摂取できます。気温や湿度によっても必要な量は変わりますね。筋肉には水分をたくわえられるため、猫の筋肉量によっても変動します。
「必要な量は自分で取るはず」と思うかもしれませんが、本当にそうでしょうか。放っておいて大丈夫なら、肥満や中毒、誤飲などを心配する必要はありません。
猫はのどの渇きに鈍感なので、飼い主が水を飲ませる工夫をすることが必要です。
猫に水を飲ませる6つの方法

1.設置場所を増やす
水の置き場所も工夫してみましょう。フードの横だけでなく、猫がよく通る場所、いつもいる場所など複数の場所に水を置いて、生活のなかで自然と飲んでもらいます。
衛生面が心配かもしれませんが、お風呂場の水を飲むのが好きな猫は多いです。「皿からは飲まないのになぜ」と思うかもしれませんが、猫は飼い主の匂いがついた水が気になるようですよ。入浴剤などを入れていないなら、飲ませてもほぼ問題ありません。
浴槽に落ちる事故が心配なため、残り湯を洗面器などに入れておくといいでしょう。
衛生面が心配かもしれませんが、お風呂場の水を飲むのが好きな猫は多いです。「皿からは飲まないのになぜ」と思うかもしれませんが、猫は飼い主の匂いがついた水が気になるようですよ。入浴剤などを入れていないなら、飲ませてもほぼ問題ありません。
浴槽に落ちる事故が心配なため、残り湯を洗面器などに入れておくといいでしょう。
2.ウェットフードにしてみる
いつもドライフードを与えているなら、ウェットフードに変えてみてはいかがでしょう。商品にもよりますが、ドライフードの水分含有量は約10%、ウェットフードは約80%です。ドライフードのトッピングとしてウェットフードを載せたり、猫用スープを足したりするのも効果的ですよ。
また、ドライフードをお湯や水でふやかすのもいいでしょう。同じエサの量でも、1回あたりの量を減らして、食事回数を増やしてみるのも効果的です。まとめて摂取するより効率的に水分を取り込むことができます。
また、ドライフードをお湯や水でふやかすのもいいでしょう。同じエサの量でも、1回あたりの量を減らして、食事回数を増やしてみるのも効果的です。まとめて摂取するより効率的に水分を取り込むことができます。
3.新鮮な水、温かい水に変えてみる
長時間、水が容器に放置されている場合、猫によっては口をつけなくなることがあります。猫の飲み水は1日に何度か取り換えて、いつも新鮮できれいな状態にしておきましょう。
自動給水器を利用すると、ろ過機能にあるものなら常に新鮮な水が飲めますし、水が流れていることに猫が興味を持つこともあります。皿からは飲まないのに、流れる水道水だと飲む猫がいますよね。
また、猫にもよりますが体温に近い温かめの水の方が飲みやすいようです。特に冬は36~38℃くらいに温めて出しましょう。
自動給水器を利用すると、ろ過機能にあるものなら常に新鮮な水が飲めますし、水が流れていることに猫が興味を持つこともあります。皿からは飲まないのに、流れる水道水だと飲む猫がいますよね。
また、猫にもよりますが体温に近い温かめの水の方が飲みやすいようです。特に冬は36~38℃くらいに温めて出しましょう。
4.器を変えてみる
猫は繊細なため、ひげが器のふちに触れるのを嫌がることがあります。ひげが当たらないように、幅広の器に変えてみましょう。少し高さがあるほうが飲みやすいので、足つきの皿にしたり台に載せたりするのもいいですね。ガラスや陶器など、素材にも猫は好みがあるようです。
猫は赤を見分けられませんが、青・緑・黄は認識できるようです。猫にわかりやすい色を選ぶと興味を持つかもしれませんね。
容器の清潔さを保つことも大切です。洗剤の匂いを嫌がる猫もいるため、汚れていなければすすぐくらいでも問題ないでしょう。どうしても洗剤を使う場合、猫の嫌いな柑橘系は避けましょう。プラスチック素材の器は匂いが移りやすく、雑菌も繁殖しやすいのであまりおすすめしません。
また、多頭飼いしている場合は、ほかの猫が口をつけた容器を避ける猫もいます。面倒でも一匹ごとに容器と水を用意するのが理想です。
猫は赤を見分けられませんが、青・緑・黄は認識できるようです。猫にわかりやすい色を選ぶと興味を持つかもしれませんね。
容器の清潔さを保つことも大切です。洗剤の匂いを嫌がる猫もいるため、汚れていなければすすぐくらいでも問題ないでしょう。どうしても洗剤を使う場合、猫の嫌いな柑橘系は避けましょう。プラスチック素材の器は匂いが移りやすく、雑菌も繁殖しやすいのであまりおすすめしません。
また、多頭飼いしている場合は、ほかの猫が口をつけた容器を避ける猫もいます。面倒でも一匹ごとに容器と水を用意するのが理想です。
5.水を替えてみる
水に溶かすタイプのまたたびが販売されています。これはかなりの効果が見込め、逆に飲みすぎてしまう心配をするほど。いつも使うのではなく、他の方法も試しながらバランスよく使用してください。
猫はカルキ臭が苦手なので、水道水の臭いが気になって飲まないこともあります。人間用のミネラルウォーターだと猫の体にはミネラル過剰なので、ペット用のミネラルウォーターを利用したり、水道水を沸かしてから与えたりしてみてください。
猫はカルキ臭が苦手なので、水道水の臭いが気になって飲まないこともあります。人間用のミネラルウォーターだと猫の体にはミネラル過剰なので、ペット用のミネラルウォーターを利用したり、水道水を沸かしてから与えたりしてみてください。
6.凍らせたペットボトルを置く
凍らせたペットボトルをトレーの上に置いておくという方法です。水を飲まない猫が、ペットボトルについた水滴はなめることに着目した飼い主さんが実行し、効果を発揮したという報告がSNS上で話題になっていました。
猫を家で留守番させるときの暑さ対策にも役立ちそうですね。
猫を家で留守番させるときの暑さ対策にも役立ちそうですね。
まとめ

猫はあまり水を飲まなくても大丈夫な体をしていますが、そのせいでのどの渇きにも鈍感。放っておくと脱水の心配があるばかりか、腎臓疾患や尿路系の病気の危険性があります。
猫の水の飲み方には好みがあるので、いろいろ試して愛猫にぴったりの方法を見つけてください。
猫の水の飲み方には好みがあるので、いろいろ試して愛猫にぴったりの方法を見つけてください。
関連する記事


猫が水を飲みすぎる原因とは?猫が1日に飲む水の量について解説
猫がたくさん水を飲み過ぎていたら心配になりますよね。あまり水を必要としない猫が水を大量に飲む原因と、飲んだ量の量り方について解説します。
執筆者プロフィール
『みんなのペットライフ』編集部スタッフが、わんちゃん・ねこちゃんの飼い方、しつけのアドバイスなど、毎日のペットライフに役立つ知識や情報をお届けします。
監修者プロフィール
18歳でトリマーとなり、以来ずっとペットの仕事をしています。
ペットとその家族のサポートをしたい、相談に的確に応えたい、という想いから、トリマーとして働きながら、獣医師、ドッグトレーナーになりました。
現在は東京でペットのためのトータルケアサロンを経営。
毎日足を運べる動物病院をコンセプトに、病気の予防、未病ケアに力を入れ、気になったときにはすぐに相談できるコミュニティースペースを目指し、家族、獣医師、プロ(トリマー、動物看護士、トレーナー)の三位一体のペットの健康管理、0.5次医療の提案をしています。
プライベートでは一児の母。愛犬はシーズー。
家族がいない犬の一時預かり、春から秋にかけて離乳前の子猫を育てるミルクボランティアをやっています。
ペットとその家族のサポートをしたい、相談に的確に応えたい、という想いから、トリマーとして働きながら、獣医師、ドッグトレーナーになりました。
現在は東京でペットのためのトータルケアサロンを経営。
毎日足を運べる動物病院をコンセプトに、病気の予防、未病ケアに力を入れ、気になったときにはすぐに相談できるコミュニティースペースを目指し、家族、獣医師、プロ(トリマー、動物看護士、トレーナー)の三位一体のペットの健康管理、0.5次医療の提案をしています。
プライベートでは一児の母。愛犬はシーズー。
家族がいない犬の一時預かり、春から秋にかけて離乳前の子猫を育てるミルクボランティアをやっています。
猫のブリーダーについて

魅力たっぷりの猫をあなたも迎えてみませんか?
おすすめは、ブリーダーとお客様を直接つなぐマッチングサイトです。国内最大のブリーダーズサイト「みんなの子猫ブリーダー」なら、優良ブリーダーから健康的な子猫を迎えることができます。
いつでもどこでも自分のペースで探せるのがインターネットの魅力。「みんなの子猫ブリーダー」では写真や動画、地域などさまざまな条件で理想の猫を探せるほか、多数の成約者の口コミが揃っています。気になる方はぜひ参考にしてみてくださいね。
※みんなの子猫ブリーダーに移動します