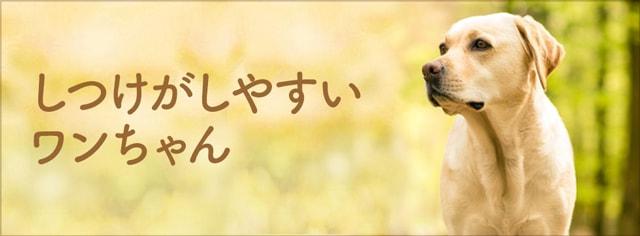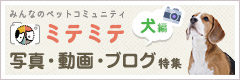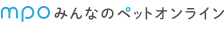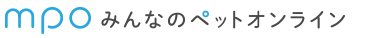日本原産で人気No.1! 柴犬の基礎知識

素朴で凛々しい表情を持つ柴犬。すっきりとして均整のとれたコンパクトな体は、筋肉質でがっしりとした骨格を持っています。堂々とした立ち姿が、日本犬らしい風格を漂わせています。
一方で、幼さの残る顔立ちや尻尾も魅力です。小さくピンと立った耳、くりくりとした丸くつぶらな瞳、クルンと丸まった尻尾と、かわいらしさも見逃せません。
凛々しさとあどけなさのギャップは、柴犬の魅力のひとつかもしれませんね。
注いだ愛情がつくりあげる信頼関係
柴犬の性格を一言で表せば「忠実で従順」という言葉がぴったりではないでしょうか。リーダーとして認めた飼い主さんや家族への献身的な姿勢は、信頼関係を分かりやすく実感できる魅力があります。
また、独立心が高いことも魅力です。常時べったりではなく、互いに独立しながらも繋がりを持てる。ペットらしいかわいらしさとはひと味異なった、親子のような家族的付き合いができる犬種です。
縄文時代から続く柴犬の歴史

その後も日本国内各地で飼育されてきた柴犬は、狩猟犬・番犬とそれぞれの時代に合わせた役割を担い、進化を遂げてきました。
しかし、明治時代には開国により洋犬の輸入が開始。交雑による雑種化が進みます。
伝統ある血脈を守ろうと1920年代後半(昭和初頭)には愛好家による保存運動が繰り広げられ、1936年(昭和11年)には「天然記念物」に指定を受けた柴犬。
主な種類としては「信州柴」(長野県)・「美濃柴」(岐阜県)・「山陰柴」(山陰地方)など、各地で繁殖が進められ、現在に至ります。
国内で飼育されている日本犬の9割が柴犬
現在「日本犬」のカテゴリにおいては、秋田犬・甲斐犬など全部で6種類がスタンダードとされております。その中でも、最も小さく最も長い歴史を持つ犬種が柴犬です。国内で飼育されている「日本犬」の9割以上が柴犬とされ、犬種全体でも「2015年JKC(ジャパンケネルクラブ)犬種別犬籍登録頭数」では5位にランクインしました。
柴犬は日本国外でも認知されている犬種で、特にアメリカでは人気を獲得しています。アメリカ・イギリス両国の畜犬団体(AKC:アメリカケネルクラブ、KC:イギリスケネルクラブ)への登録はもちろん、世界的な畜犬団体であるFCI(国際畜犬連盟)にも公認犬種として認定されています。
「キツネ顔」と「タヌキ顔」

キツネ顔
縄文柴と呼ばれる祖先犬に近いタイプです。面長で細長い顔、オオカミのように大きな歯、引き締まった細身の体。「信州柴」がこのタイプに近いとされています。
タヌキ顔
新柴犬、弥生柴犬とも呼ばれるニュータイプ。まんまるの顔、筋肉質でがっしりとした体、キツネ顔に比べると体が小さめです。「美濃柴」がこのタイプにあたります。
柴犬は「小型犬?」「中型犬?」
チワワやポメラニアン、マルチーズなどの小型犬にくらべ、柴犬は大きなサイズの体を持ちます。
しかしながら、柴犬は小型犬とされることもあります。その理由は、日本犬各種のなかでは最も小さいため、小型と呼ばれていた名残です。小型犬・中型犬の定義で曖昧さが残る現状では、いくつか気をつけておきたいポイントがあります。
ペット可のマンション・アパートの入居条件
物件によっては、「小型犬のみ可」という物件があります。例えば「〇〇kg」までなど、具体的な記載があれば判断もつけられますが、具体的な条件が設定されていない物件もあります。不動産管理会社や大家さんに相談しましょう。
トリミングサロン・ペットホテルの料金
各施設の料金は、一般的に犬種・サイズによって定められています。犬種など細かく指定されていれば問題ありませんが、「小型」など見た目で曖昧な料金設定をしている店舗もあります。不明な点は事前に問い合わせるようにしましょう。
ドッグラン・ドッグカフェ内で
ドッグランにおいては、犬のサイズによってエリア指定をされることがあります。サイズの違いによるケガなどのトラブルを避けるためです。まずは、施設管理者に確認を。
犬と一緒に入店できるカフェなどの施設でも入店・入館条件のチェックを忘れずに。

ちなみに、秋田犬など大型のイメージがある日本犬のなかでは柴犬は最も小さいサイズの体です。
目安とされる体のサイズ
体高:38~41.cm(オス)、35~38cm(メス)
体重:9kg(オス)、8kg(メス)
体高より体長がやや長くしっかりとした骨格を持ち、バランスのとれたコンパクトな体つきをしている柴犬。小さな三角形の立ち耳と目がかわいらしく、丸くカールした尻尾は15もの種類があるとされています。
柴犬の被毛の特徴
バリエーション豊かな4つの毛色

柴犬の代表色、赤毛
キツネのような美しく薄い茶色です。柴犬では最も多く、約8割がこのカラーを持つとされています。赤毛は、年齢を重ねるにつれ色が薄くなることが特徴です。早い段階で綺麗な赤毛をしている場合は、だいたい2~3歳あたりから白っぽくなっていきます。
赤毛同士の交配を重ねた場合には、世代が進むにつれ白っぽい色の個体が生まれやすくなるので、黒毛の柴犬と交配を行い色素の退化を補っています。
「まろ眉」がかわいい、黒毛
黒毛の柴犬は、全体の1割程度とされます。裏白の部分以外は頭から尻尾まで、すべて黒毛に覆われています。
特徴的なポイントは、目の上にある斑点。はっきりと出ている茶や白の斑点は「まろ眉」とも呼ばれ、かわいらしく人気です。ちなみに、赤毛にもよく見ると斑点があります。
真っ白な被毛が目をひく、白毛
体全体が白毛で覆われています。白毛は黒毛よりも生まれる確率が低く、全体の1割未満です。赤毛または黒毛同士で交配した際に、遺伝子の影響で白毛の個体が生まれると言われています。
3色混合の希少な存在、胡麻毛
赤毛・黒毛・白毛が混じっている被毛を「胡麻毛」と呼びます。バランスよく混ぜ合わさった深みのある色合いが魅力の胡麻毛は、非常に珍しく希少な存在です。
黒色が強い場合は「黒胡麻」、赤色が強い場合「赤胡麻」と呼ばれます。成長の過程において、遺伝子的に優勢である赤に変色する場合があります。
忠実で従順な柴犬の性格

祖先の血が色濃く残っている?
野生のなかでは、犬は「群れ」を成して生活を送ってきました。信用できる存在は「リーダー」です。群れを率いる強いリーダーに従い、群れを守ることで生き抜いてきたのです。いわゆる「縦社会」的な関係性のもと、リーダーに従う習性は今でも残っています。
忠実で従順ながら、一方で「個」としての高い独立心を持つ柴犬。
常に何かへ興味を持つ好奇心、そして外を駆け回ることを好むという特徴は、獲物を探し追い立てていた狩猟犬時代から受け継がれている本能です。
柴犬の子犬を迎えよう

心身ともに充実した子犬を選ぼう
社会化期は、犬の本能である「群れ」で暮らすルールを覚える大切な時間です。社会化期に親きょうだいと過ごすことで、犬としての習性そして「社会性」を身につけていきます。あまりに早く親きょうだいから離されてしまった場合、犬としての習性やルールを理解できません。結果、自身が犬であるという意識が希薄になり、群れのリーダーに従うという習性が身につかないままなので、しつけのしにくい子になってしまいます。
「社会化期」を健やかな環境下で過ごした子犬を迎えることが、愛犬と楽しく生活する大切なポイントです。
健康的な子犬を選ぶためのチェックポイント
・人間に慣れている。極度に吠えたり震えたりしていない。
・柴犬らしく、締まった筋肉質な体をしている(見た目より重さがあるくらい)。
・被毛が密集して生えていて、皮膚のトラブルがない。
・歯茎がピンク色。かみ合わせもよい。
・肛門の周辺が汚れていない。
・肉球に、ツヤと弾力がある。
子犬を迎える3つの方法

ペットショップ
ペットショップ最大の魅力は「アクセスの良さ」。日本は個人で経営している店舗はもちろん、ホームセンター内に併設している店舗も多く、足を運びやすい環境にあります。気軽に見学できるのはペットショップならではのメリットです。
ブリーダー
計画的な繁殖のもと、親犬やきょうだい犬たちと育てられていくので、社会性が身についた子犬が多いのも大きなメリットです。また、飼育のプロでもあるブリーダーから実践的なアドバイスを受けることもできます。また、中間業者を挟まないため、ペットショップと比較すると安く購入できるケースが多々あります。
里親になる
ご家庭の事情などで、残念ながら飼い続けることが出来なくなってしまった愛犬の里親探しを行っている方は少なくありません。各地で定期的に開かれている譲渡会をはじめ、近年では保護犬を紹介する里親募集サイトでも募集が頻繁に行われています。

『みんなのブリーダー』は全国のブリーダーの子犬を紹介する国内最大のブリーダーズサイトです。
専門ブリーダー直販なので、健康でかわいい子犬を安心価格で購入できます。
柴犬の習性に合わせた室内環境の整備

家族全員が共通したルールのもとでしつけを行うことにより、子犬は家族全員に等しい関係性で接しやすくなります。しつけたい内容も入りやすくなるので、育てやすくいい子へと成長していきます。
しつけのルールに加え、居住空間を整理・整頓して、危険性のあるものを極力置かない、危険な箇所へと立ち入らせないようにするなど、危険防止の対策を取りましょう。
習性1:甘噛み・かじり癖
柴犬は、気になったものをかじる習性を持ちます。まして子犬は、甘噛みするのが通常です。家具やコードなどは、事前にガードしておく必要があります。
かじるタイプのおやつやロープのおもちゃなどを与えて、「噛みたい」「かじりたい」欲求を解消させましょう。また、甘噛みは放置しないことも大切です。噛む癖が抜けないと、成犬になった時にも噛みつくようになってしまいます。
噛む・かじる時の対処法
何かを噛んだ時には、すぐに「ダメ」とはっきり短く叱り、犬の口元を握って噛めないような体勢にします。こうすることで、犬は「吠える→口元を抑えられる→抑えられたくないから、吠えない」という学習をしていきます。
遊んでいる時に、もし噛んだらすぐ遊びをやめるなど、「すぐ」に行動することがポイントです。時間が経ったあとに叱っても、効果は期待できません。
習性2:収集癖
落ちているものを拾い集め、巣(テリトリー)に持ち帰る習性があります。穴を掘って巣をつくり、物を蓄えておくという野生における習性によるものです。
部屋のなかに物を置いておくと持ち帰ってしまうので、極力室内には物を置かないようにしましょう。口にしてはいけない食べものや観葉植物には、特に注意が必要です。
迎える前に用意しておくペット用品
・サークル(ケージ)…柴犬にとって、落ち着ける巣となるサークルは必ず用意しましょう。
・トイレ…柴犬は野生における習性・本能が残り、巣となる場所において排泄をすることはほとんどありません。そのため柴犬には、巣となるサークルからは離れた位置にトイレを設置します。
・キャリーバッグ・クレート…動物病院やお出かけの際、移動用に必要です。
・フード、食器…食器は、「フード用」「水飲み用」をそれぞれ別に用意しましょう。
・首輪・ハーネス(胴輪)、リード…散歩時に必須のアイテムです。金具や接続部分がしっかりとしている製品を選びましょう。
・お手入れ(グルーミング)用品…コームブラシ、スリッカーブラシ、ラバーブラシ、ファーミネーターなど
・おもちゃ…好奇心旺盛な柴犬にとって、おもちゃで遊ぶ時間は楽しく大切なものです。
柴犬の飼い方

サークルは落ち着ける「巣」
設置する場所については、
・エアコンなどの風が当たらない
・家具から離れた位置
・適度に会話が聞こえるリビング(テレビや音響装置の横は避ける)
といった「犬の所在を確認でき、適度な距離感がある」場所がおすすめです。
サークルに慣れてもらうには、サークル自体にいい印象を持たせることがポイントです。フードをサークルの中で食べさせるなど、工夫をしましょう。サークル内で落ち着けるようになると、急な来客時にもおとなしく休んでいられます。有効に活用しましょう。
室内でトイレをきちんとできるように
トイレ用サークルが用意できない場合は、何らかの形でトイレ用スペースをつくり、四方を囲んでトイレをつくりましょう。そこにトイレシーツを敷き詰めればトイレの完成です。四方を囲むと柴犬はその場所を「トイレ」の場所だとはっきり認識するようになります。
外でトイレ(排泄)するようになると……
柴犬は成長にともない、習性的に外で排泄をするようになる犬が多い傾向にあります。とはいえ、外で排泄する癖がつくと、排泄する機会が散歩以外にない状態になってしまいます。
何が困るかというと、飼い主さん・柴犬ともに負担が大きくなることです。
・飼い主さんからすれば、悪天候の日でも散歩に出かけなければならない
・柴犬からすれば、家で留守番する場合は、排泄を我慢することになりがち
などが考えられるほか、公共性を考えても外で排泄させることはあまり好ましいとは言えません。
子犬を健康に育てるための食事量

迎えた当初は以前の環境と同じように
急に食事の環境を変えてしまうと、体がついていかず体調を崩してしまうことがあります。迎えた当初、少なくとも数日間は以前の環境と同じ形で食事を与えましょう。同じフード・同じ量・同じ回数・同じ時間・同じ形状(お湯でふやかすなど)です。
じょじょに新たな食事のスタイルを身につけさせよう
その後は、新しいフードをこれまでのフードに混ぜて与えるなど、徐々にシフトしていきます。正しい習慣を身につけさせるため、食事は「決まった時間、決まった場所」で食べさせることがポイントです。水は常時新鮮なものを用意します。食事量はしっかりと管理し、もし食べ残した場合はすぐに片付けましょう。
食事の回数は、
・生後6カ月まで:1日3~4回
・生後6カ月以降:1日1~2回
が目安です。
子犬期は、健やかな成長のために栄養摂取が重要です。バランスのとれた食事を与えるようにしましょう。
子犬の体重の変遷
・オス 約9kg
・メス 約8kg
です。生後1カ月ずつ1kg体重が増加すると、適切な成長であるとされています。ちなみに、標準とされる体長はオス38~41cm、メス35~38cmです。
柴犬は骨密度が高いため、標準体重より若干重くなる場合もあります。そのため、すぐに肥満を心配する必要はありません。もし、「体重が増えない」「食が細い」という場合は、様子を見ながら、一度医師に相談しましょう。
毎日の運動が欠かせない柴犬

また、飼い主さんのジョギングを兼ねて一緒に走ったり、ドッグランで自由に走らせたりすると良い運動となり、散歩の質も向上するので理想的です。
散歩は「1日1時間」が目安
柴犬の筋肉質な体をキープするためには毎日の散歩が理想的です。柴犬の旺盛な好奇心を満たすために、日々散歩コースを変えて変化をつけると良いですよ。
散歩量の目安は毎日1時間以上。朝・夕の2回に分けてもOKです。
散歩デビューは、ワクチン接種が終わり獣医師のゴーサインが出てからにしましょう。散歩の時間は生後3~5カ月は20分ほど、生後5カ月以上からは成犬と同様1時間程度を目安にしてください。まずは外の環境に慣れさせることが大切です。
上手に留守番をさせるためのコツ

留守番に慣れさせていくには、「必ず飼い主さんが戻ってくる」ということを愛犬に学習してもらう必要があります。
「外出する」アピールをしない
「行ってきます」「ただいま」といった挨拶や、勢いよくドアを開閉するなど、いかにも「外出する」素振りを見せてしまうと、賢く察しのいい柴犬は飼い主さんが出かけると察知してしまいます。飼い主さんが出入りするサインとなるような言動は避けましょう。
トレーニングの方法としては、愛犬の目の前でドアから出て短時間で戻るという行動を繰り返します。何も言わず、何もせず、自然な行動の中で出かけて、いつの間にか戻ってきているという状況が望ましいです。
一連の状況に慣れてくると、飼い主さんがドアから出ても不安感を覚えることなく、落ち着いた状態でいることができます。結果、長時間の留守番にも段々と適応できるようになっていくという訳です。
留守番させる際には整理整頓が大切
愛犬に留守番をさせる際には、
・新しい水やフードを用意する
・トイレシーツを変えておく
・退屈しないよう、おもちゃを出しておく
といった基本的なことに加え、室内の整理整頓が大切です。
柴犬は行動範囲が広いので、しっかりと対策を取りましょう。
・散らかり防止:テーブルに何も置かない、棚の扉を閉めておく
・誤飲を防ぐ:物を出しておかない
・危険の回避:台所(ガスや刃物)・水場(溺れる)・階段(転落)などの危険エリアには立ち入らせない、電気コード(感電)をかじらせない
エアコンによる室温管理も大切です。特に暑い夏場は、被毛の厚い柴犬にとっては苦手とする季節です。熱中症にかかりやすくなるので、注意しましょう。冷気は部屋の下部にたまりやすいので、あまりに冷えすぎないよう風向きを調整するなど配慮を。冬場は皮膚が乾燥しないよう、湿度管理が重要です。
子犬時における「しつけ」の重要性

もともとリーダーには非常に従順な柴犬ですから、しっかりと「主」と「従」の関係を構築できればよきパートナーとなります。
忠誠心、独立心ともに高い柴犬をしつけるベストタイミングは、性格が形成される子犬期です。一度身についた生活習慣やクセは成犬になるとなかなか直らないため、性格形成の時期に教えてあげると後々スムーズなのです。
また、柴犬はリーダーに忠実な犬種なので飼い主さんが「リーダー」であると認識させる必要があります。自分より下の存在だと認識されると言うことをきかなくなってしまいます。人間と一緒に暮らすために必要なマナーやルールをきちんと身に付けさせるためにも、柴犬をしつけるときは「先導する」意識で接しましょう。
ひとたび飼い主さんを信頼できるようになれば、ペットとして模範的なパートナーとなってくれるでしょう。
ブラッシングで被毛と皮膚の状態をキープ

被毛の状態を健やかに保つには、無駄な毛・死毛を取り除くことがポイントです。こまめなブラッシングは毛玉の発生を防ぎます。
また、通気性を確保することによる皮膚の健康維持、皮膚の血行促進による新陳代謝の向上、皮脂の効果的な分泌による毛ヅヤの向上など、多くの効果をもたらします。
「通常期」と「換毛期」におけるブラッシング
最初はブラシやコームなど、ブラッシングの用具を見せながら慣らしていきます。慣れてきた段階で、徐々に体に触れていきましょう。短時間で、一カ所ずつ行うとよいです。毛並みに沿って、ブラシを入れていきます。毛がもつれている箇所は、無理にブラシを入れません。
通常時、ブラッシングの頻度は週1~2回程度。下毛がごそっと抜ける「換毛期」は、毎日ブラッシングをしましょう。
換毛期は必ずしも時期は決まっていませんが、季節の変わり目(特に春や秋)に多いとされています。換毛期は、一気に毛が抜けるわけではありません。頭部・胸部・背中・脇腹・足など、部位ごとに抜けていきます。一気にブラッシングしないようにしましょう。ちなみに、上毛は一年中生え変わります。
ノミやダニからも身を守るシャンプー
被毛や皮膚を清潔にし、体臭を防ぐ役割のあるシャンプー。ノミやダニからも、体を守ります。シャンプーの頻度は、月1回程度がベストです。シャンプーをしすぎると、皮膚を保護するための皮脂まで洗い流してしまうため、かえって皮膚の状態が悪くなってしまうことがあります。ちょっとした汚れの場合は、濡れタオルで拭いて汚れを落としましょう。
日々、健康状態をチェックしよう

皮膚疾患に気をつけたい。柴犬がかかりやすい病気
ほかの犬種と比べ、強い体質を持つとされる柴犬。一方で、かかりやすい病気がいくつかあります。特に気をつけたいのは、皮膚疾患。アレルギー性皮膚炎が好発しやすいので、注意が必要です。
アレルギー性皮膚炎
体に侵入したアレルゲン(カビ・ノミ・ダニ・花粉・ハウスダスト・食べもの)に過剰反応を起こし、皮膚の炎症が起きます。強いかゆみが起こるため、体をかきむしったり、皮膚が赤くなっていたらこの病気の可能性があります。
膝蓋骨脱臼(しつがいこつだっきゅう)
先天的または後天的な要因により、膝のお皿(膝蓋骨)の骨がずれてしまう病気です。膝が腫れたり、足を引きずっている時は疑いましょう。
角膜炎(かくまくえん)
ウイルス感染・自己免疫性・特発性など、様々な要因で角膜に炎症が起こる眼病です。目に入った異物を取り除こうとした際に、角膜に傷がついてしまう場合もあります。症状としては、目やにがたまりやすい、日常的な目の充血がみられます。
頼もしきパートナー・柴犬と豊かな時間を

古来より残る習性や本能と上手に向き合いながら、しっかりとしつけを行い、柴犬と充実した生活を送っていきましょう。
 柴犬の性格や飼い方のポイント〜俊敏さと賢さを生かすためにしっかり運動しよう
柴犬の性格や飼い方のポイント〜俊敏さと賢さを生かすためにしっかり運動しよう古来から親しまれる日本の犬の代表が柴犬です。凜々しいたたずまいと小さな身体に秘めた闘争心は番犬としても優秀で、トレーニングによりその賢さはより一層光ります。この記事では柴犬の性格や飼い方につい...
 柴犬のカットの必要性について
柴犬のカットの必要性について柴犬は抜け毛の多い犬として有名です。特に換毛期のときの量は多く、毎日掃除をしても追いつかないほど。「いっそのこと、もっと毛を短くしたら掃除の手間が減るんじゃ……?」などと思う飼い主さんもいるので...
 知っておきたい柴犬の室内飼いのメリット・デメリット
知っておきたい柴犬の室内飼いのメリット・デメリット柴犬はもともと猟犬や番犬の役割を担い、屋外で飼われていました。しかし、最近では住宅事情や犬に対する考え方が変化し、室内飼いする人が増加中です。今回の記事では、柴犬を室内飼いするメリットやデメリ...
 忠誠心あふれる柴犬に育てるためのしつけ、3つのポイント
忠誠心あふれる柴犬に育てるためのしつけ、3つのポイント国内外で人気の柴犬。飼い主に忠実な性格で人気を呼んでいますが、独立心も高いので、しつけは飼い主さんが「リーダー」となって柴犬を先導する必要があります。柴犬の特性に合わせた上手なしつけのキーワー...
 散歩上手はしつけ上手! 柴犬の散歩で主導権を握る方法
散歩上手はしつけ上手! 柴犬の散歩で主導権を握る方法昔から日本の山岳地帯で猟犬として重宝されてきた柴犬は活発なので毎日の散歩が必須です。一方、外に出ると好奇心旺盛でいろいろなところに飼い主さんを引っ張っていこうとすることも……。犬の自由にさせると...
 他の犬とはちょっと違う? 柴犬向けトイレトレーニング法
他の犬とはちょっと違う? 柴犬向けトイレトレーニング法柴犬は古くから屋外で飼われてきましたが、最近では室内飼いする方も増えてきました。ここでは柴犬の特性に合わせたトイレトレーニング(しつけ方法)をご紹介します。ほかの犬種とくらべるとしつけが少し難...

『みんなのブリーダー』は全国のブリーダーの子犬を紹介する国内最大のブリーダーズサイトです。
専門ブリーダー直販なので、健康でかわいい子犬を安心価格で購入できます。

すべてのワンちゃん・ネコちゃんがいつまでも健康でいられるように。
安心・安全にこだわったドッグフード・キャットフード、ペット用品の通販ショップです。
柴犬のブリーダーについて

魅力たっぷりの柴犬をあなたも迎えてみませんか?
おすすめは、ブリーダーとお客様を直接つなぐマッチングサイトです。国内最大のブリーダーズサイト「みんなのブリーダー」なら、優良ブリーダーから健康的な柴犬を迎えることができます。
いつでもどこでも自分のペースで探せるのがインターネットの魅力。「みんなのブリーダー」では写真や動画、地域などさまざまな条件で理想の犬を探せるほか、多数の成約者の口コミが揃っています。柴犬が気になる方はぜひ参考にしてみてくださいね。